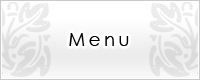灰被りの春 中学一年・夏
あの頃の松浦と西崎は馬鹿だった。
中学一年・夏
思いっきり脇腹を蹴られてオレは部室の床に倒れ込んだ。
ギブスが外れたばかりの腕を強か打ち付けて、一瞬息が詰まる。
蝉の鳴き声が五月蝿い。
噴き出す汗は暑さのせいだけではないけど。
「おら、ゴメンナサイはよ?」
促されるまま謝罪しようと開いた口に、ローファーの先を突っ込まれた。
埃とよく分からないゴミの苦い味に、えずきそうになる。
「ほ…へんなはい…」
オレは、もっと馬鹿だった。
一ヶ月前オレのせいで抗争が起きかけた。
ダチとナンパしたグループのうちの一人の女と仲良くなり、ホテルに転がりこんだ。
しかしホテルまで行ってそいつが、ウチと敵対してる浦和北中の番の女だということが分かった。
そこで何もせず帰れば…帰れれば、リンチされアバラや腕を折ることも、入院で出席日数が危うくなり早くもダブりの危機に陥ることも、頭同士の話合いとかで松浦さんに怪我させることも、今こうして西崎さんにシメられることもなかった、のに。
「元気が有り余ってるみてーだな、ここによ?」
「痛…っ!あっ…ぐ…」
股間を踏みつけられ、一瞬で脂汗が噴き出した。
退院した途端にこれだ。
見舞いに来たときやたら冷たかったから予想はしていた。
だから正直ガッコに来たくなかったんだ。
悶絶していると足の力を弱められ、ぐりぐりと動かされる。
先程よりはずっと少ない痛みと、また思い切り踏まれるかもしれない恐怖を感じているのに、その中に確かに快感を見付けてしまう自分の浅ましさに顔が熱くなる。
「西崎、さ…」
「踏まれておっ勃てやがって。溜まってんのか?変態」
足の甲で股間を撫で上げられ、ぞく、と体が震えた。
「また厄介な女とやっちまわねぇように、ここで出しちまえよ」
西崎さんとはたまに、していた。
抜き合いだったり、オレが一方的に抜かれたり、まあただの遊びでオレはおもちゃだ。
だけど、学校でするのは初めてで、オレは狼狽えた。
「ここで、すか」
「言ってんだろ早く下脱げよ」
見下ろしながら、西崎さんは右足のローファーを脱いだ。
このまま足で抜くつもりであることを知り、嫌々ベルトのバックルに手を掛けて、そこで躊躇して指が止まる。
「早くってんだろ」
強く踏まれて、思わず悲鳴を上げてしまった。
もたもたとベルトを緩め、ボンタンを脱ぐ。
オレがトランクスに指を掛ける前に、待ちくたびれた西崎さんの足の指がゴム部分を引き下げた。
半勃ちのチンコの先が飛び出し、オレは赤面して思わず西崎さんを仰ぎ見た。
薄い唇の片端がくっと持ち上がる。
「情けねぇツラ」
西崎さんのこの表情をみるのは、何度目だろう。
嘲るような、同情するような、傷ついたような不思議な笑顔だった。
「あ…」
その顔の下の感情について考える前に足を動かされ、オレはいつも通りただ身をよじることしかできなくなった。
ティッシュなんか持ち歩いてないオレはトイレでちんこを拭いた。
ただでさえ手ほどは器用に使えない足で散々焦らされ、オレは西崎さんの靴下を汚して大量に射精した。
結局ずらしただけの状態でイかさられたので、トランクスにも付いてしまった。
右手を怪我しているオレは西崎さんの言う通り溜まっていたのだ。
少し迷ったが、オレはそれを脱いで鞄に押し込む。
ついでに洗面台で汚れた顔を洗う。左手だけしか使えないので学ランまで濡れた。
擦り傷に水が滲みる。
部室に戻ると、ドアはオレが開けたまま半開きになっていた。
西崎さんは窓の下に置かれたベンチに腰掛け、壁にもたれて外を見ている。
何十分シゴかれていたのか、外は日が傾いて夕焼けになっている。
いつの間にかグランドではミニゲームの紅白戦が始まったらしく、わーわーと騒々しい声とスパイクが土を蹴り駆け回る音がしていた。
「松浦ぁ―…」
誰かが松浦さんにパスしたらしい。声が一層大きくなった。
物憂げにボールの行方を見守っていた西崎さんが、窓に向けて体を捻る。
逆光の夕陽に照らされて、その横顔がオレンジのふちに飾られていた。
ぼうっとそれを見ていると、バスッという音のあと歓声が上がり、西崎さんが少し笑った。
「西崎さん」
声を掛けるとはっとした様子でこちらを見る。
「松浦さんのゴールっすか」
何気なく聞くと、西崎さんは傷付いたような顔で睨んだ。
なにか悪いことでも言ったかと思い緊張したが、すぐに西崎さんは微笑して立ち上がる。
「帰っか。ラーメン奢ってやるよ」
いつものラーメン屋にはすでに3人の客がまばらに座っていて、オレたちはカウンターの端に並んで腰を下ろした。
「チャーシューメン二つ」
席につくなり西崎は一番高いやつを勝手にオレの分まで注文した。
礼を言うと、唐突に指の背で頬の擦り傷を撫でられた。
「見せてみ」
顎を軽く掴まれて顔の角度を向けられる。
目元の痣だとか鼻の切り傷をまじまじと観察され、オレは周りの目が気になった。
他人からはただの先輩後輩のじゃれあいに見えるかもしれないが、さっきあんなことをしたあとだから心臓がどきどきと鳴った。
オレも反対に西崎さんの顔を見る。
整った顔をしてると思う。
中二とは思えないくらい背も高い。しかもまだ伸びてるらしい。
脚なんてウチのガッコの誰より長い。
女にも不自由しないのに、なんでわざわざオレにちょっかいかけるのか、いまだに分からない。
オレは西崎さんにやられるままにしてるだけでホモじゃねえけど、西崎さんはホモ…とまではいかなくてもバイってやつなのかもしれない。
でも本当に好きなのはオレではない気がしていた。
「…松浦さんも怒ってました?」
切れた唇の端を押されながら、痛みを耐えてずっと気になっていたことを聞いた。
西崎さんは、あーと無意味な声を上げて手を離した。
「あいつは忘れてんじゃねえか」
「忘れ…」
「あいつは一ヶ月も前のことなんか気にしねぇの。分かるだろ?あの調子だからよ」
西崎さんはいつも松浦さんのことを話すとき妙に嬉しそうにする。
「男らしいっすもんね」
「オレと違って、か?」
いえ…と口篭ると、西崎さんはコップを持って笑った。
「お前ほんと松浦好きな」
含みのある言い方で、オレは一瞬口篭る。
「キ…キライなわけないでしょう。一年みんなの憧れっすよ」
「憧れねえ」
意味ありげに反芻し、西崎さんはコップに口を付けた。
なんだか大きな誤解をされてる気がする。
「それはそうと、お前高校どこにすっか決めてんのかよ」
言い返そうと口を開いた瞬間話題を変えられ、オレは誤解を解くタイミングを失った。
「いえ…まだ一年だし…」
「オレたちは蕪双にすっから、オメーも来いよ。どうせダブりのお前が行けっとこなんて他にねーだろ」
まだダブりと決まった訳ではないが、それを差し引いても確かに言う通りで、オレはハアと間抜けに返事をして頷いた。
「蕪双は最近はイマイチだけどサッカー強ぇしよ…。タダシ、お前が入学すっときオレらは何年だ?」
「え…一年遅れてっから…三年、すか」
と、そのとき目の前にチャーシューメンが置かれた。
「そ、オレが怒ってんのはそういうことよ。オメーの戦力期待してんだぜ、オレも松浦も」
そう言いながら、片手では箸が割れずもたついてたオレからそれを奪い割ってくれる。
「馬鹿だよなお前」
「…ウス」
中学の部活より、高校の方が重要で、それなのにオレは松浦さんたちと一年しか一緒にやれない。
それを二人は惜しいと思っていてくれる。
俯いていると、西崎さんは自分のチャーシューを一枚オレのラーメンの上に置いてオレの頭を撫でた。
怪我をしてからオレは色々なことを腹の中に溜め込んで思っていたより消耗していたらしく、それだけのことで涙ぐんでしまった。
それを隠すために湯気が立ち上るチャーシューメンを急いですする。
口の中が切れて、ただ痛くて味なんか分からなかった。
オレたちは、馬鹿だったんだ。
NEXT