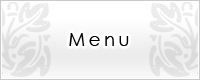灰被りの春 高校一年・秋
高校一年・秋
黒い服を着た大人たちが笑っている。
親戚の五周忌の法事で、オレは埼玉に来ていた。
いくら神奈川に越したって、埼玉で生まれた以上この土地から完全に逃れることは出来ない。
オレは隅の壁にもたれて、大往生だったじいさんを悼むことなんて頭になく騒ぐ親戚たちを遠巻きに見ていた。
中学までは悪ガキで、今は愛想ゼロのオレはあんまり可愛がられてるとはいえず、誰にも構われない。
それに輪をかけて、オレは法事が嫌いだから今日は一段と仏頂面のはずだ。
賑やかでも、喪服を着た人間が集まり坊さんが経をあげると、どうしても久志の葬式を思い出す。
オレは自分の服を見下ろす。
こういうとき、いつも着てる学ランは喪服になる。
しばらくその黒を見ていたが、耐えきれなくなり立ち上がってどっかのばばあと談笑している母ちゃんに近付いた。
「母ちゃん、オレ体調悪いから帰る」
周囲のばばあたちが口々に引き止める言葉を発する。
母ちゃんは呆れた顔でバッグから新幹線の切符と家の鍵を出して渡してきた。
オレはおざなりな挨拶を一同に済ませ、喪服を着たまま外に出た。
駅行きのバスに揺られ、ぼうっとして外の景色を見る。
この道は何度か通ったことがある。
あいつらのバイクのケツに乗って走ったことも。
そういえば松浦のバイクに乗っていたときに、もう少し先で警察に見つかり、無免二人乗りだったから必死にまいたこともあった。
その後合流した西崎が笑うから、オレたちも深夜の訳のわからない路地みたいなところで腹を抱えて笑ったっけ…。
今となっては苦い思い出だ。
オレはポケットに突っ込んだ拳に力を込めた。
「次は、埼玉スタジアム、埼玉スタジアム――」
聞き覚えのある名前に、オレははっとした。
見えた円形の巨大な建物に、「高校サッカー埼玉県予選」ののぼりが掲げられている。
オレは落ち着かない想いで無意味に辺りを見渡したりしてみたが、結局理由もなく降車ボタンを押した。
熱に浮かされたようにふらふらとスタジアムの前に立つ。
立て看板に書かれた今日のカードを確認すると、蕪双は第一試合でとっくに終わっていた。
安堵し、その直後自分が何がしたいのか分からず唇を噛む。
だけど、何をするというわけではないが観戦していくことにした。
試合は後半戦が始まったばかりで、スコアは1-0だった。
観客席は選手の身内しか来ていないらしく、空席が目立った。
どうやら重要なカードではないらしい。
そういえばどちらもあまり聞かない名前の学校だ。
オレは席には着かず後ろの立ち見席でぼんやりと試合を見た。
本当なら、オレもここで試合をしたはずだった。
紫のユニフォームを着て、あいつらと一緒に…。
今思えばおぞましいことだ。
それを夢見てた自分に反吐が出る。
知らず握り締めていた拳を開いたのは、にわかに観客が沸いたからだ。
見ればゴールの中にボールが転がり、シュートを入れたらしい選手に仲間が群がり抱きついている。
実況によればこれでスコアは2-0。
勝敗は決まったようなものだ。
そう考えたのはオレだけではないらしく、客席の何人かが立ち上がり帰る気配を見せた。
もしかしたら知り合いがいるかも、とやや緊張して通路を上がる人の顔を盗み見る。
すると前の方の席に座っていた茶髪の男が立ち上がり、そのジャージに書かれている文字が読み取れるようになりオレは体を強張らせた。
面白くもなさそうな顔をして、ポケットに手を突っ込みうつむき加減で歩くその男を、よく知っていた。
「西崎、さん」
考えるよりも先に名前を呼んでいた。
何気ない様子で顔を上げた西崎の顔色も変わった。
「タダシ…」
呼び返されて、オレは夢から醒めたようにハッとして踵を返し、さっき来た道を早足で戻った。
「待てよ、タダシ!」
足は昔から西崎の方が格段に早くて、少し駆け足にしただけであっけなくオレは捕まってしまった。
メイン通路から外れた、関係者しか通らないような薄暗い通路に引っ張られて壁に押し付けられた。
「何しに来たんだよ」
きつく睨まれても、もう怖くはない。
こいつらの強さなんて薄っぺらだ。
あの頃のような輝きはもう感じなかった。
「なんでもないっすよ…」
顔を逸らしたが、すぐに髪を掴まれて向き直される。
オレは痛みに顔を歪めて思いっきりメンチを切った。
「生意気になりやがって」
面白くなさそうに西崎は言った。
「昔はオレの下でアンアンよがって可愛げがあったのによ」
その言葉に脳裏にこいつに良いように弄ばれた日々が蘇り、かっとして逆に西崎の胸ぐらに掴みかかった。
「もう弱っちいガキじゃないんす。あんたなんかもう先輩とも思ってない。今度はオレがやってやりましょうか」
そう軽口を叩くと、西崎はきつく睨んだあと一瞬表情を歪める。
「やってみろよ」
そして挑発的に笑った。
試合中はほとんど人通りのない、ロッカー室近くのトイレの最奥の個室に二人で収まり鍵を掛ける。
立ったまま、西崎のジャージのファスナーを下ろす。
案外その音が大きく聞こえて、オレはヒヤッとした。
目線を上げると冷めきった西崎の目とぶつかる。
「どうした?ビビったか」
唇だけで笑われて、オレはやけになってTシャツを捲くりあげた。
男と寝たのは西崎が最初で最後で、オレは西崎を抱くにあたって昔のことを回想するしかなかった。
昔西崎がオレにしたように体をまさぐったつもりだが、反応は無いに等しく、乾いたままの体をいたずらに撫でるばかりだ。
平たい胸を必死に弄るオレの指を冷ややかに見下ろしていた顔が、ふいに失笑を漏らす。
「お前、女にもこうしてんのかよ?」
馬鹿にする声色に、悔しさで顔が熱くなる。
「どうせ下手ですよ、あんたみたいに節操なくないんで」
オレは一旦体を離し、西崎のジャージを下着ごと股間まで引き摺り下ろした。
足を掛け踏んで地面まで下げると、西崎は自分から足を抜いた。
その積極性にまで腹が立ち、肩を掴んで乱暴に便座に座らせる。
「こっちの役も慣れてるんすか」
嘲るように言ってオレも前を寛げる。
「…それよりよ、ちゃんとムケて良かったな」
質問を無視して、オレの股間を見て西崎は鼻で笑う。
オレは顔に熱が集まるのを感じながら、その口に人差し指と中指を近付ける。
西崎は一瞬躊躇ったあと大人しく咥えた。
フェラチオさせようかとも思ったが、万が一噛まれたらと考えると出来なかった。
オレは口内の指をめちゃくちゃに動かしながら、左手で自分のをシコった。
「松浦…さん、ともやってんすか?」
細められていた眼が再び鋭くなる。
漏れる息が荒いのは息苦しさだけではないらしい。
「良かったじゃないですか。あんた松浦さん好きでしたもんね」
舌の奥を爪で引っ掻くと、えずいて喉がひくつく。
根元まで濡れた指を引き出すと唇との間に透明な糸をひいた。
西崎は口元を拭うと、貯水タンクにもたれ掛かり顔を背ける。
オレは屈みこみ西崎の右足を肩に乗せ、薄い尻を割って唾液で塗らした指をゆっくり埋めた。
長身の体が強ばり、便座を掴む指が白くなった。
「なんだ…処女なんすか」
あえて女みたいな言い方をした。
「うっ、せ…ッ」
しこりを見つけてそこを擦りあげると、肩にかついだ脚がびくんと跳ねる。
「今のは痛かったんすか?それとも気持ちよかった?」
「るせぇ…ってんだろ…ッう」
だかこのまま善くしてやるつもりはない。
起き上がると左足の膝を開いて、西崎の体の上に被さるような体勢をとった。
「…ゴム付けろ」
「持ってないっす」
西崎は投げ出された自分の鞄を顎でしゃくった。
「財布」
教えられたままに鞄を探ると、クリームソーダの長財布に確かにコンドームが挟まっていた。
未だに遊びまわってる証拠だ。
あんな事件を起こしておいて、いい気なもんだ。イラっときた。
封を開け立ち上がったチンコに被せ、ケツに押し当てると流石に顔色が変わった。
少しめりこませれば、こじ開けられる感覚と刺される予感からか、西崎は唇を噛む。
「力抜いてくださいよ、優しくしてやりますから」
言い終わらないうちにオレは一気に腰を進め根元まで挿入した。
「はっ!……く、あ…」
「嘘ですけど」
十分にはほぐしていない穴はきつく、西崎は背けた首筋に脂汗を流しながら痛みに耐えた。
オレもあまりの圧迫感に、ゆるゆると腰を動かしながら西崎のモノをシゴく。
「あ、ぐ、…ち、くしょ…」
「は…キツ…」
手を上下に動かしながら、胸を舐めてやる。
一瞬ぴくんと体が跳ねて声が漏れた。
手と舌、腰の動きを繰り返していると、だんだん中がひくつきほぐれてくる。
「は、あ、ク…っ」
横顔が痛みと湧き上がってきたらしい疼きに歪む。
何処か遠くを見てるような目が少し濡れている。
生理的なものだと分かっていても、何故だかざわついた。
オレは体を起こすと膝裏を押さえ、自分勝手に激しく腰を動かす。
「うっ…ア…ッ」
その振動で便器から落ちそうになった西崎は、左手を便座から離しオレの腕にすがりついた。
何故か一瞬心臓が苦しくなり、それを誤魔化すために憎まれ口を叩く。
「い、いからってそんなしがみ…っ、つかないでくださいよ。動きにく、い、じゃないっすか」
「いいわけ、ねっ…だろ、クソ…ッ」
突くたびに二の腕に西崎の指が食い込んで痛む。
肉と肉がぶつかるパンパンという乾いた音と、二人分の荒い息がトイレ内に響いた。
背筋を震わす快感にじわりと汗を掻き、オレは学ランを脱いで後ろへ投げる。
脚を抱え直して、いつの間にかオレの脚の方が太くなっていることに気付いた。
突きながら、久志のことを思った。
いつもオレのあとを付いてきた久志。
松浦のようにかっこよくなりたいと言っていた久志。
西崎の足の速さを羨んでいた久志。
松浦と西崎に苛められ、オレに助けを求めて泣いていた久志。
「んっ…う…」
「はっ…」
息が苦しい。
昂っていくにつれ、 貧血のときみたいに頭が白くなる。
記憶は久志からずれていき、どうでもいいような光景を脈略なく引き出していた。
オレがリンチされたとき、助けに来た松浦と西崎がやたら頼もしく見えたこと。
西崎の家の近所のサテンで食べたモーニングのメニュー。
ゆで卵を剥く西崎の長い指。
汚れたオレのトランクスと西崎の靴下を下校路途中のドブ川に捨てたこと。
ローファーとボンタンの裾の間から一瞬見えた西崎のくるぶしの白さ。
夕陽に染まるグランド。
閃光のようなドリブル。
鮮やかなオーバーヘッド――
「ふっ…」
くぐもった熱い息を口内に感じ、オレは無意識に西崎にキスをしていたことに気付いた。
はっとして顎を掴んだ手を離すと、西崎は驚いた顔をしていた。
その直後、脱力したようにふっと笑う。
「…情けねぇツラ」
見覚えのある、痛みを堪えるようなその笑い顔に、オレは喉の奥に何かが突っ掛る感覚を覚える。
(どっちが)
西崎が昔オレによくしたように亀頭部分には軽く爪を立てると、短く低く悲鳴が上がり、オレはその締め付けで達した。
体を離すと、萎えたチンコがずるりと抜けた。
「…ど下手くそが…」
開放された脚を投げ出して、西崎は乱れた息の合間に吐き捨てた。
その股間はとっくに萎えていた。
オレはチンコからゴムを抜いて結ぼうとしたが、上手く指先が動かずもたつく。
「殺人犯に優しくする義理はないっすからね」
西崎はさすがにカッときた様子で口を開いた。
だがすぐに思い直して唇を噛み、視線を逸らす。
「ちっとは気ぃ済んだかよ」
オレは瞬間的に湧き上がった怒りに任せ、西崎の顔にコンドームを投げつけた。
口を縛っていないそれは額で爆ぜて、精液が整えたリーゼントを汚し頬を流れた。
「済むわけねえだろ!久志は…久志は死んだんだ!あんたと松浦が殺した…!」
西崎は一瞬屈辱に奥歯を噛み締めたが、伝う精液もそのままに冷静な目でオレを見た。
悔しさよりも、何か歯痒そうな、傷付いたような、同情するような変な目だった。
事件の真相を問い詰めたときの松浦も、同じ目をしていた。
オレの方が加害者になったような気になって、急いでずり下がったズボンを上げ床に落ちた学ランを掴む。
「松浦に近づくなよ」
背中に投げつかられたその言葉には答えずにトイレを飛び出す。
早足で歩くと涼しくなった空気が汗ばんだ体を冷やし、オレはまた喪服を着込んだ。
オレは、馬鹿だったんだ。
NEXT