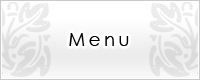人でなしの恋
「おい、早く決めろよ」
「うるさいなぁ。焦るなよー」
田舎町の酒場のカウンターで、店には不似合いな4人組みが本のようなものを覗きこんでいた。よく見れば少年2人、奇妙な生き物を連れた少女1人、中年の男が1人と、不思議な組み合わせの連れ合いである。
「こちらなどはどうですか?"山岳地に生えるスパイスの原料となる花を採ってくる"」
「まぁ、お花ですか?素敵ですわ!」
「たまにはそんな仕事もいいかもな~」
わぁっ、と盛り上がる3人から覆面の少年が依頼台帳を奪う。
「"1本につき3ゴルゴル"?そんな子供の遣いみたいな仕事できるかよ」
「もう、サルトビったら…」
4人が覗きこんでいるのは料理のメニュー表ではなく、冒険者や賞金稼ぎ向けの仕事の依頼が記されている台帳であった。この店は酒と料理を出す傍ら、そうした仕事の斡旋も行っている。
アデュー、パッフィー、サルトビ、イズミ、そしてハグハグの一行はアースティアを救う戦いを終えた後も共に冒険を続けていた。
アデューは一人前の騎士になる修業として、残りの3人はいつかそれぞれあるべき場所に戻る前に世界を知る為に、当てもない旅に出たのだった。しかしそれは半ば建前で、実際はこの面子で過ごす時間が心地いいという理由が大きい。
「サルトビはいらっしゃらないのですか?」
「4人で行くような仕事でもねぇだろ」
「うむ…それはそうだが…私たちがいない間どうする気だ?」
「並行して別の仕事に取り掛かる。そうじゃねぇと路銀が尽きるだろ」
現実的な発言に、3人はう、と言葉に詰まる。
一国の王女を連れているにも関わらず、相変わらず資金に困る状況が続いている。
楽しそうなこと、正義感をくすぐられることがあれば採算度外視で無邪気に首を突っ込むアデューとパッフィー、そのパッフィーにとことん甘いイズミ、というメンバーではそれも仕方のないことで、毎回金策に頭を悩ませるのは決まって現実主義のサルトビであった。
「兄ちゃん達、どの仕事にするか決まったかい?」
恰幅の良い店のマスターがアデューとパッフィーの前に料理を置きながら声を掛けてきた。
大盛りのパスタから薄く立った湯気、それに乗って漂うスパイスの香りに、アデューは金欠も忘れて唾をごくりと飲んだ。
「うまそー!いただきまーす!」
「この大飯食らいが財布を切迫すんだよなぁ」
「うん?なんは言っは?」
すでに料理しか眼中にないアデューを、サルトビは呆れた顔で見る。マスターはアデューの見事な食べっぷりに気を良くし、大きく笑った。
「この仕事を受けたいのだが…」
「その他にもうひとつ。なんか賞金首とか、気の利いた仕事はねぇのかよ」
「おお、兄ちゃん運がいいねぇ。そこにはまだ綴ってない、新しいのがあるんだよ」
ちょっと待ってな、とイズミとサルトビの分の料理をカウンターに出し、マスターは店の奥に下がった。
「本当に1人で行くのですか?」
「厄介そうだったら情報収集でやめとくからよ。心配いらねぇよ」
「あったぜ、これだ」
マスターが持ってきた手配書をサルトビが受け取り目を通す。
「1,000ゴルゴルか、まぁまぁだな…邪竜族か」
「はりゅうぞふぅ!?」
「ハグゥ!?」
口いっぱいに料理を詰め込んだままアデューが叫び、その声に驚いてハグハグが飛び上がる。
「汚ねぇな!」
「まら生き残っへやがったのか!」
「アデュー、食べるか喋るかどっちかにしなさい」
「1人1人とどめを刺した訳じゃねぇんだ。ちょっとは残党がいてもおかしくねぇさ」
アースティアを征服しようとした邪竜族とアデューたちリュー使いが死闘を繰り広げたのは2年前のことであった。それから邪竜族による事件は聞かれなかったが、僅かに残った者が何処かでひっそりと息を潜めている可能性は十分にあった。
「近くの森で目撃情報があってな。一体だけだと思うが…」
「親父、こいつにするぜ」
「おっやるか。生死は問わないから思いっきりやっちまってくれよ」
太古の時代から邪竜族と攻防戦を繰り広げてきたアースティアの人間にとって、彼らは絶対的な悪であった。邪竜族だ、というだけで事件を起こさなくても殺害可の討伐依頼が出る。
「そいつの特徴は」
「外見はほとんどエルフなんかと同じだ。肌の色もな。人間で云えば20前後の兄ちゃんって歳らしい」
「肌も?」
「…なぜその外見で邪竜族だと分かるんだ?エルフか人じゃねぇのか」
「顔にな、鱗があるんだとよ」
マスターはカウンターに肘を付き自分の頬を指でなぞる。
「ここんとこに銀の鱗がな」
4人は以前戦った邪竜族の姿を思い返した。下位の邪竜族は大きなトカゲが竜の様な姿をしていたが、皇帝の周囲を固めていた上位の邪竜族は鱗の生えた人型をしていた。
「上位邪竜族か…強いかもな」
「サルトビ、くれぐれも…」
「分かってるって」
「姫、サルトビはいつものようにうまくやってくれますよ」
心配そうに見つめるパッフィーをイズミが優しく説得する。
「ええ、でも、なんだか妙なんですもの。人と同じ肌の色の邪竜族なんて、居たかしら」
その後マスターと二つの依頼について確認し食事を済ませ、宿で休んだ。
アデューたちが受けた仕事の納期に合わせ、3日後に宿で落ち合うことにした。
翌朝サルトビが1人離れるときも、パッフィーは心配そうに何度か振り返った。
邪竜族の残党が居るという森は、町のすぐ裏手にあった。
この近さを思えば、町民が不安になり、たった一件の曖昧な目撃情報だけで手配書を発行してしまうのも無理はない。
(探す方は困るんだけどよ)
森、と一言で言っても面積は広大で、鬱蒼と茂った草木に阻まれ視界も良くない。
宿を出発して約4時間。時折虫や鳥の鳴き声は聞こえるが、他に動くものは風に揺れる草や木の葉だけで、動物や人、モンスターの気配とはまだ出会っていない。
あまり人が入らず道らしい道も無いと聞いていたため、ギャロップはむしろ邪魔になると判断して置いてきた。サルトビは酒場のマスターに渡された大まかな地図を片手に獣道らしきところを1人歩く。
邪竜族が目撃されたのは森の中心部にある池だと言う。
飲み水や調理用水の確保の為、旅人は休むとき出来るだけ水辺に腰を下ろす。邪竜族残党はその池の傍で一晩を過ごしたのだろう。そのまま何処かに旅立ったとしても、焚き火の跡などの痕跡でそうと分かるはずだ。
そして水を飲みたいのは動物やモンスターも同じである。サルトビは今辿っている獣道がその池に続いていると読み、黙々と歩みを進めていた。
(そろそろか…)
水の流れる音がする。
小さなせせらぎが集まり、池を形作っているのだろう。徐々に音が大きくなっていき、サルトビは周囲の気配に意識を配る。
もし一体だけなら、爆裂丸を持つサルトビは難なく倒すことが出来るだろう。だが目撃された者以外に複数体いて、もしドゥームを所持していたら…。初めて訪れる土地での戦闘である、どうなるか分からない。
そのとき、池の方向から落ち葉を踏む音がした。
反射的にサルトビは近くの木の影に身を隠す。素早い動きながら足音一つ立てないのも忍の術の内だ。
動物か、魔物か、人か―それとも例の邪竜族か。
池はまだ見えず、サルトビはそっと腰のクナイに手をやりながら聴覚を研ぎ澄ます。
落ち葉と土を踏む音、虫の泣き声、衣擦れの音、風に葉が擦れる音、水音―。
気配は一つだけで、対峙しても勝てると踏んだサルトビは、相手とコンタクトを取ることにした。
クナイを握り直し、声をあげる。
「誰かいるのか」
ぴたりと足音と衣擦れが止む。
草木の揺れる音と水音だけが二人の間に流れる。
「その声…」
気配が口を開いた。
「もしかして…サルトビか?」
聞き覚えのある声が森の奥から聞こえ、クナイを握った手が降りる。
「まさか…」
動揺を隠せないまま硬直していると、気配が動き出し足音が近づいてくる。サルトビがゆっくりと木の陰から出ると、痩躯の男が立っていた。
口元から上の顔は被ったマントに隠れて見えないが、忘れられない黒衣と背格好にサルトビは息を呑む。
「ガルデン…」
「…久しぶりだな」
お互いに、再び相まみえるとは思っていなかった。
かつての敵同志、どんな言葉を交わせばいいのか分からず水音だけが間に流れる。
「…アデューたちは一緒ではないのか」
「あ、ああ。別の仕事に行ってる」
「そうか」
「てめぇはこんなところで何してんだ?」
そう問うと口ごもった後に、ちょっとな、と歯切れの悪い回答が返ってきた。
その反応を奇妙に思いながら、サルトビは何気なくガルデンの背後の池の様子を窺った。
池の上には木が無いため、陽の光が水面に反射し輝いているのが見える。ふと気付いてサルトビは再びガルデンに問いかけた。
「なんでこんな晴れた日にマントなんて被ってんだ。暑苦しい」
「貴様に言われたくはないがな」
冗談めかしてそう言い返され、いつも覆面と鉄兜を身につけているサルトビは言葉に詰まりフン、と視線を外した。話題が無いのも居心地が悪いが、まるで友人のように会話するのもむず痒い。
「相変わらず口が減らねぇな」
「…相変わらず、か…」
反芻した声は、心なしか沈んでいてサルトビはその唇に目をやった。
僅かな沈黙の後、その端正な唇から溜め息のようなものを吐き、ガルデンはマントに手をかけた。
「どうだ、存外変わっただろう」
見慣れたはずの顔が陽の下に晒され、サルトビは本日二度目の絶句をした。
サルトビの見開いた目を見つめながらガルデンは小さく笑い、右頬の銀色の鱗がきら、と光った。