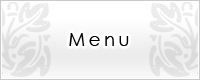スターチスのくちづけを
スターチス
学名:Limonium(イソマツ科リモニウム属の総称)
別名:ハナハマサジ(花浜匙)
花期:春
多年草または一年草で、まれに低木または亜高木である。
薄紫色の小さな花をつけることが多いため、英名ではシーラベンダー (Sea Lavender) やマーシュローズマリー (Marsh rosemary) と呼ばれるが、ラベンダーやローズマリーとは類縁関係にない。
枯れても色が変わらないため、ドライフラワーに用いられる。
花言葉は
そこまで読んだとき、下校のチャイムが鳴り、私は手にした植物図鑑を本棚に戻した。
帰り支度を始める司書を横目に、自分の教室へと向かう。
日が陰りだした廊下を歩くには、リボンを外した胸元が少し涼しい。
グラウンドや体育館には部活中の生徒はいるが、校舎にはほとんど残ってはおらず、誰も居ない廊下に私の足音と、微かな彼女の音だけが響く。
階段を降りるとその音は大きくなり、私は頬が緩むのを抑えられない。
彼女が苦しみもがく音。私に怒り憎む音。
教室のドアを開ければ、薄い鉄に肉がぶつかるガタンガタンという音が一瞬の静止の後、一層激しくなる。
激しく揺れる掃除用具入れのロッカーに近づき、取り巻きに作らせた合鍵を差し込む。
かちりと回すと同時に体を横にずらすと、勢いよくドアが開き白いセーラー服が倒れこむ。
固いタイルに強か体を打ちつけた彼女が、低く呻いた。
彼女を初めて見たのは入学式だった。
両親に連れられて校舎をに向かう、どこにでもいる新入生。
取り立てて美人な訳でもなく、似た知り合いがいたわけでもない。
それでも何故か、ひどく、ひどく懐かしいと感じた。
真新しいセーラー服に包まれた、柳の様に細くしなやかな肢体、雪の様に白い肌、栗色のセミロングの髪、活発で少し生意気そうな声。
その後ろ姿を見る為に足が止まっていることも、父に促されるまで気が付かないほど、自分の感情に戸惑っていた。
動揺し震える足を動かし、彼女の斜め後ろを歩く。
両親と話しながら歩く彼女のスピードは遅く、父の歩幅に合わせて進む私は徐々に距離を詰めていった。
視界に入る彼女の角度が変わり、初めてその顔を見る。
白く滑らかな頬に細い顎、少し上向きの尖った鼻。
その下に鎮座している小振りの唇に、見てはいけないものを見た様な気になり、一瞬眼を逸らした、
それでも、どうしても気になり盗み見るように視線を戻す。
彼女を追い越した瞬間、その眼がふいに私を見た。
短い睫毛に縁取られた、大きく釣り目がちの眼。
瞬間、強烈な既視感は確信へ変わり、震える唇を開きかけた。
しかし私が声を上げる直前、背後から甲高い人を呼ぶ声がして、彼女の眼はそちらへ移る。
友人の姿を見つけた彼女は、私を捕らえた眼を細め、秘めるべき唇で名を呼び返した。
原因不明の郷愁が、私の居ない人生を謳歌していることへの焦燥と嫉妬に変わった。
「あの娘、生意気ね」
中学から一緒の取り巻きにそう呟けば、幼稚な苛めが幕を開けた。
最初の苛めは単純で簡単なものだった。
入学して3日目、登校してきた彼女は自分の机に置かれた花瓶を呆然と見ていた。
活発で勉強も容姿も並、性格も悪くない彼女は、自分が苛められるなんて思っていなかったはず。
立ちつくす彼女を見て、堪え切れず取り巻きがくすくすと笑いだす。
それに気付いた彼女が、花瓶を掴み大股で近づいてくる。
「あんたらがやったの」
平均よりもやや高い背で、椅子に座る私達を見下ろす。
「あたしが何かした?」
「分からない」
取り巻きが揃って黙る中、私が答えた。
彼女のあの眼が私を射抜く。
「誰でも良かったって訳」
「そんなことない。貴女じゃなきゃ」
花を引き抜き、彼女は剣で斬る様な動作で横一字に花瓶を振った。
私たちに中の腐りかけた水が掛かり、取り巻きたちが一斉に悲鳴を上げる。
「ふざけんなよ」
吐き捨て、彼女は踵を返して教室から出ていく。
私は何だか嬉しくなって、青臭い水が口に入るのも構わず、笑った。
倒れ込んだ拍子に頭に被せられていた掃除用のバケツが転がった。
そこには「死ね ブス」と取り巻きの汚い字で書かれていて、彼女を貶める以外の意味は込められていないと知りつつも、余りの的外れさに苦笑する。
私の制服のリボンで後ろ手に縛られ、暴れて疲労した体では上手く起き上がれないらしく、彼女は芋虫のようにタイルの上で身をよじっている。
スカートが捲れ上がり、白い太ももが露わになっている。
屈みこんで内腿に手を差し込むと、びくりと体が跳ね、うめき声を大きく上げる。
彼女の小さな肩を掴んで、仰向けにさせた。
馬乗りになって髪に指を通すと、怒りに荒げた息が口に押し込まれた彼女のリボンにくぐもる。
鞄から鋏を取り出すと、刃物を見た彼女が目を見開いて暴れた。
「動くと耳が切れるわ」
セミロングの髪を掴み、鋏を入れる。
じゃき、と軽い音がして一房の髪が彼女の頭から離れる。
「あっ」
首を振った拍子に刃先が白い頬を抉り、一筋の傷を付けた。
うっと彼女が短く呻き、わなわなと震えながらも暴れるのを止めた。
大人しくなった彼女の髪を、私は黙って切り続ける。
西日が彼女の流れる赤い血、短くなっていく髪を染め、私は訳の分からない郷愁にかられ熱い息を吐く。
最後の一房を切り落とし、すっかり黙ってしまった彼女の口からリボンを取り除く。
水分を吸わないサテンの生地と彼女の唇を、唾液の糸が繋いで、切れた。
腕の拘束も外し彼女の上から退くと、教室のタイルに散乱した栗色の髪の中心で彼女は胎児の様にうずくまる。
「そっちの方が似合ってる」
彼女は怖々自分の髪に触れた。
ちくりと毛先が掌に刺さり、大事に伸ばした髪をベリーショートまで切られたことを知った彼女は、涙を溜めた眼で私をきつく睨んだ。
嗚呼、やっぱり眼を、私は何処かで見たことがある。
「何様のつもりなの…」
彼女は屈辱と怒りに震える声を絞り出す。
「女王様のつもり?」
「貴女が一番的外れね」
彼女の瞳を覗きこめば、憎悪の炎の中に私がいる。
そうよ、それでいいの。
リボンの食い込んだ痕を撫でながら、彼女の手の甲に、主君にかしずく騎士のように口付けた。
彼女の手がぴくりと跳ねる。
憎しみと同調の狭間の戸惑い。
それに私はかしずく。
貴方は私の女王様。
Fin.