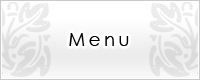86:献花
――お前の鎌は何の為にある。
少年は問いかけました。
――人間の魂を刈るためさ。
死神は答えました。
――俺の魂も刈るのか。
少年は問いかけました。
――いいや、お前の魂は特別に綺麗だから、閉じ込めてずっと見ていよう。
死神は答えました。
――いいだろう、その代わり、もう村の者には手を出さないと。
――ああ誓おう。私にはお前がいればそれでいいのだ。
死神が少年に口づけをすると、少年はたちまち石になってしまいました。
「祠へ御神酒を置いてきてちょうだい。死神に会わないようにね」
幼い息子の頭に頭巾を巻きながら、母は義務のように言った。
龍神沼。
それはこの忍びの隠れ里、モモチの砦の聖域である。
数百年前に邪竜族を討った勇者の一人である“サルトビ様”が、この世に災いをもたらす死神を鎮めるため、自ら人身御供になったという伝承がこの村には伝わっていた。
「死神は夜にしか来ないんでしょ?」
「そうよ、サルトビ様に会いにね」
「なんで?」
大きな目で見つめられ、母はまた悪い癖が始まった、と小さく溜息を漏らした。
一番好奇心旺盛な時期である。
気になることがあれば身近な大人になぜ?と訊くのが最近の癖であった。
「昼間だと里の人間と出会っちゃうから。…ほら、早くしないと日が沈んじゃう。続きは帰ってから」
相手をすると永遠に続く質問地獄をうまく撒いて、母は少年を送り出す。
少年は酒の瓶を抱いて、玄関から飛び出した。
沼の中心の祠に、石にされたサルトビ様を讃え祀ってある。
と、云われているが現頭領である少年の父など「良く出来た彫刻だ」と評した程、皆所謂“昔話”としか捉えていない。
村に代々伝わるリューを操る人物だという話だが、そのリューも何処かへ消えてしまっていた。
アースティアを救った勇者であることに間違いはないのであろうが、伝承の中で死神の存在が唐突すぎる。
なんらかの要因で早世した英雄を神格化するために作られた話ではないか、というのが大人達の暗黙の共通認識だった。
兎に角、この聖域に立ち入れるのは頭領の家系の者だけと決められており、祠の管理は一族に託されていた。
一年に一度の鎮魂の儀を除けば、普段の管理は御神酒と供え物の交換と掃除くらいの簡単なものである。
8歳の誕生日を迎えてからは、少年は率先して供え物を持っていった。
大人たちが何と言おうと、少年にとっては祠の石像はまごうことなき“石化した英雄”だった。
開きかけた手、滑り落ちたばかりの形の覆面の皺、静かな決意を感じさせる、死神を見据えていたであろう目。
どれも作り物には思えなかった。
今にも動き出して悪を斬り、一族の往くべき道を指し示してくれそうな生気を全身に湛えているように、少年には見えた。
村の者皆が崇める勇者の世話を出来ることに淡い誇りを感じ、少年は小さな胸を熱くさせて沼へと歩く。
何者かの陰に気が付いたのは、集落を抜けたときだった。
杉林の中を誰かが歩いている。
木の影に隠れて良くは見えないが、どうやら大人の男の様だった。
村の者であったら声を掛けて来るだろうし、何より男からは異質な雰囲気がしていた。
向こうからは、開けた平地を歩く少年の姿は良く見えるだろう。
気味の悪さに少年が早足になると、男の陰も歩むスピードを上げた。
「少年」
不意に陰が声を上げた。
自分を呼んでいることは、見渡すまでもなく分かった。
少年は足を止めて男に向き直る。
草を踏む音がして、男が林の中から出でる。
黒い服を着た、若い男だった。
衣服や顔立ちから異国の者だと一目で分かったが、鎌を持った骸骨でないことに一先ず安堵した。
「どこへ行く」
落ち着いた声色である。
「龍神沼の…」
素直に答えかけ、はっと気付いて途中で口を噤んだ。
「ひ、秘密!」
異国人に隠れ里の聖域を教える訳にはいかない。
覆面の下でぎゅっと口を結んだ少年に、男は微かに目を細めた。
死神ではないにしろ、この隠れ里に外部の人間が居るのは不可解なことだった。
それでも、少年は恐怖は感じなかった。
鎧の類を一切身に付けず、薄そうな黒い布製の服だけで細身の体を覆っている無防備な印象がそうさせたのかもしれない。
異様で、どことなく浮世離れした男の存在感は、少年の恐怖心ではなく、好奇心を煽った。
「お兄ちゃんの耳はどうして尖ってるの」
男が二の句を告ぐ前に、少年の無邪気な質問が飛び出した。
突拍子もない問いに、青年はいささか面食らったようだった。
「…お前たちには聴こえない音まで聴くためだ」
初めて知る別の人種の体の不思議に、少年は目を輝かせた。
好奇心に火が付いた少年は、矢継ぎ早に質問を浴びせかける。
「どうして髪の色が銀色なの」
「人間ではないということが、一目で分かるように」
「どうして黒い服を着ているの」
「…死んでいった者たちへの、弔いの証に」
「どうしてそんなに目が大きいの」
「見たい者の顔がよく見えるように」
「どうしてそんなに睫毛が長いの」
今度こそ男は苦笑し、マントを翻した。
「供え物なら、一緒にそこの花でも摘んで行ったらどうだ。きっと喜ぶ」
黒い手袋が指した先に振り返れば、白い菊の群生があった。
なぜ自分の目的を知っているのかと問いかけようと顔を戻すが、男はまた杉林の仲に隠れて歩き出していた。
少年はその場で逡巡していたが、菊は確かに美しかった。
なにより、「サルトビ様が喜ぶ」という言葉が気を引いた。
迷っていた少年は、ついに踵を返し白い花畑へと駆けて行った。
きぃ、と小さな音を立てて、祠の戸が開かれる。
陽の光が射し込み、闇の中から白い少年のかたちが浮き上がる。
扉を開けたまま、ガルデンは祠の中へ足を踏み入れる。
中にはガルデンと変わらない背丈の、少年の石像が安置されていた。
ガルデンはしばらく沈黙してその石像を見詰めていたが、あるとき決意の表情で腕を挙げ、呪文を唱え始めた。
掌から眩い光が放出され、曲線となって像を取り囲む。
詠唱が終わったが、腕からは細い光が出続けている。
「途中、里の子供に会ったぞ」
そのままの姿勢でガルデンは語り始めた。
「初めて会ったときのお前と同じ年頃だ。足止めしておいたが、後で此処へ来るだろう。早く終わらせねばな」
何を言おうが、石の瞳は変化を見せない。
「此処では私は“死神”と呼ばれる。勇者や聖騎士といった華々しい呼び名より、死神の方が肌に合う。可笑しいだろう。私はお前に生きていて欲しかっただけなのに、だ」
それでもガルデンは懺悔するように、言い訳じみた告白を続ける。
「本当だ。私が生きていくにはお前の存在が必要だった。幾つもの命を紙屑のように燃やした私に追い縋り、責めたのはお前だけだった」
黒衣の下、薄い胸の筋肉の溝に冷たい汗が落ちるのが分かる。
「己の罪に気付いた私の命は、お前に裁かれるためにあるのだ。だがお前は私に背を向けて、平凡な生活に収まろうとした。お前は私を裁くために生きてきたのではないのか、と。お前には堪ったものではないだろう。実のところ、ただの寂寥、嫉妬…。私はとんだ自惚れをしていた。お前の手は何も私の血で汚れる為にあるのではなかった。愛した女、我が子を抱くことだって出来たはずだ。こんな簡単なことに気付くのに、いや…本当は知っていたのかもしれない。認めたくなかっただけなのだ」
掌から放出される光が淡く、弱くなり、止まった。
「愛していたから、お前を石にした。だが…」
ガルデンは深い溜息をつくと、色が戻り始めたサルトビの頬に触れ、硬い唇に口付けた。
「お前は幸せになるために生まれてきたのだ」
サルトビの眉根がぴくんと動く。
短い髪がしなやかに黒く撥ねている。
頬の傷が血の色を滲ませる。
瞳に光が戻る。
首から上が人の色を取り戻した瞬間、サルトビは激しく咳き込んだ。
唇の間から白い砂が吐き出される。
ガルデンは苦々しくそれを見ていた。
「なんで、今更術を解いた」
苦しげに、下を向いたままサルトビがそう問いかける。
「上手く説明がつかない。だが、解くなら今が限界なのだ。これより遅いと、二度とお前は人の体に戻れぬ。アースティアは随分、平和になり、もう私の目がなくとも…」
ガルデン、と激しい口調でサルトビが名を呼ぶ。
「利口ぶってんじゃねぇ。俺だって今更、幸せになれるなんて思っちゃいねぇよ」
己を睨む青緑色の瞳。
この鋭い視線を、ガルデンは長い間求めていた。
「何故、俺を人に戻した」
胸が詰まるのを感じながら、ガルデンは最後の言葉を搾り出した。
「愛しているからだ」
サルトビは腰のポーチからクナイを取り出し、手の感覚を確かめるように一度、二度とその柄を握った。
ガルデンは濡れた瞳でそれを見詰める。
「お前の手で、終わらせてくれ」
長い睫毛の先に付いた雫が、終幕を飾っていた。
少年が龍神沼の入口をくぐると、祠の前に異様な、しかし見慣れた人影があった。
古い型の忍び装束、細身の体躯、短く切られた髪、それは―
「サルトビ、様…?」
細い体を重そうに引き摺り、サルトビが振り向く。
深紫の忍び装束と、白い顔が返り血に染まっていた。
対岸の少年からはよく見えないが、サルトビの足元に先程声を掛けてきた黒衣の男が横たわっているのが分かった。
夥しい血液が岩場から澄んだ沼へと流れ落ちている。
「その人、死神だったの?」
少年が死体を見るのはこれが初めてだった。
忍者といえど幼い子供。臆しても不思議ではない。
だがガルデンの死体と血濡れのサルトビからは、悪意を感じなかった。
この光景の真意を、自分は知っておかなければならないと、少年の中の頭領の血が静かに沸いていた。
「違う。ただの…ただの人だ」
まだ何か問いかけようとする少年を制すように、サルトビは続けた。
「頭領の子供だろう」
声が半ドーム状の岩場に響く。
訳も分からないまま、少年はこくんと頷いた。
それを見たサルトビの表情が緩む。
クナイを握った右手が白く変質し、腕から離れたのを遠目に見た。
硬い足場にぶつかって砕け散る音が少年の耳にも届いた。
「里を…アースティアを頼んだぜ」
そう言って笑ったサルトビの顔に、左頬の線傷からヒビが広がる。
白く硬い石となったサルトビの体は足元から崩れバラバラと音を立ててガルデンの死体の上へ倒壊した。
同時に、何処かでガコン、という轟音がくぐもって聞こえた。
水面が波打ち、足元の岩場が揺れ、少年は思わずその場にしゃがみこむ。
見れば、祠を祀った岩場が崩れていく。
祠と、二人の男の死体が沼に呑み込まれて行くのを、少年は大きな目をいっぱいに見開いて、確かに胸に刻んだ。
崩壊の音が消え波が治まった頃、少年は立ち上がり引き寄せられるように小舟に乗った。
小さな手で舵を握り、精一杯漕ぎ出す。
心臓が壊れそうな程に鳴っていたが、頭は冷静だった。
沼の中心、岩場があった場所で、舟を止める。
そこに、一枚のカードが浮いていた。
これこそ一族の守り神、爆烈丸のミストロットだったが、少年はまだその価値を知らない。
ミストロットを拾い上げ、水中を覗き込む。
白く濁った水に、赤い血の筋が一本通っていた。
舞い上がった砂が沈殿しても、二人の死体は崩れた岩場の下だろう。
少年は改めて手にしたミストロットを見た。
濡れた瀑烈丸は、水面の輝きを反射してきらきらと光っている。
しばらくその輝きに魅入られていた少年だったが、ふと思い出し、傍らの白に視線を移した。
ミストロットを大事に懐に仕舞い、青い匂いのする花を抱き上げる。
そして、少年は両手いっぱいの白菊を水面へ投げた。
幸せになるはずだった、二人の勇者へ、ただの人間二人へ、精一杯の追惜を込めて。
FIN.