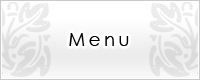44:歌声
歌を忘れたカナリヤは後ろの山に棄てましょか
いえいえ それはなりませぬ
歌を忘れたカナリヤは背戸の小薮に埋めましょか
いえいえ それはなりませぬ
歌を忘れたカナリヤは柳の鞭でぶちましょか
いえいえ それはかわいそう
歌を忘れたカナリヤは
久方ぶりに会った少年は、ガルデンに刃を向けなかった。
多少の憎まれ口を叩いたものの、まるで確執など無かったように、単なる不仲の知人のように接した。
他のリュー使い達と同列に扱い、共に戦った。
その代わり、一度も眼を合わせようとはしなかった。
「私を許したのか」
彼らと別れるとき、ガルデンはそう投げかけてみた。
瞬間、集団の空気が張り詰める。
サルトビは足を止めたが、振り向きもしなかった。
肩越しに不安げな視線を投げてくるパッフィーの背を、アデューはひどく優しく押した。
パッフィーと眼を合わせ、それからサルトビを、そしてガルデンを見た。
この世界が好きだとガルデンに語ったときと同じ笑顔だった。
ガルデンが和解を望んで訊いたと思っているのだ。
アデューを裏切ることを解っていてなお、ガルデンは黙っていた。
彼の眼に、自分がどんな顔で映っていたのかガルデンは分からなかった。
欺くために笑ってさえいたかもしれない。
「お前ら先に行け」
ガルデンに背中を向けたまま、サルトビは同行者達を促した。
「そう…じゃあ、ここでお別れですね」
「サルトビ、ガルデン、元気でな!」
アデューの様に笑っている者もいれば、不安そうに見る者もいた。
サルトビがどんな顔でいたのかは、分からなかった。
それぞれが乗ったギャロップが駆け出し、遠ざかっていく。
姿が見えなくなっても、サルトビは背を向けたまま押し黙っていた。
「私を許したのか」
蹄の音が聞こえなくなった頃、ガルデンは再び問いかけた。
「…簡単に言うな。ただ…」
答えても、サルトビは変わらずこちらを見ようともしない。
「復讐は忘れることにしたからよ。てめぇも好きに生きろよ」
ガルデンは、体の芯がざわつくのを感じた。
「本心か」
再び、沈黙が流れる。
ガルデンは今更、サルトビの背が伸びたことに気が付いた。
甲冑の背に走っている浅い刀傷も、3年前には無かったと思う。
「てめぇの知ったこっちゃねぇだろう」
苦く、そう吐き捨ててサルトビは歩きだそうとした。
過去を振り捨て行くその腕を、ガルデンは反射的に掴んだ。
驚いて振り向いたサルトビと、ようやく、3年ぶりに眼が合う。
ガルデンは、今度は確かに自分が笑っていることが分かった。
「あっ…うっ…」
いつの間にか日が落ちていて、岩の隙間から差し込む月明かりがサルトビの揺れる背を薄青く照らしていた。
彼は数時間に亘りガルデンに犯され続け、男を受け入れる場所でない小さな穴からは血が流れ細い腿を汚す。
傷付けられれば、手段はなんでも良かった。
肌を見られるのを厭う潔癖な少年は、男に力ずくで汚されるのが最も堪えるだろうと、それだけの理由で犯した。
それだけのはずだった。
だが、マスクを剥げば屈辱に唇を噛み、服を脱がせば羞恥に肌を染め、快感を教えれば困惑し震え、痛みを与えれば苦痛に声を上げる、その一挙一動にいつの間にかガルデンは制止が利かなくなっていた。
全裸に剥かれ、何度も体位を変え貫かれ、もうサルトビには抵抗する体力が残られていない。
裸の肌はごつごつとした岩に擦られいたるところに血が滲んでいる。
今は腰だけを高く上げされられたうつ伏せの姿勢で、右腕を手綱のように捉えられ体を揺らされていた。
その細い二の腕にはかつてガルデンが斬り落とし、なんとか繋ぎ合せた際の傷が歪に残っている。
少年の白い肌に引き攣る痕は痛々しく、ガルデンは胸にちくりと違和感を覚える。
「っ、良い眺めだな」
「は…っ」
乱れた息の間にガルデンが煽る。
サルトビは喘ぎながら、額の下に置いた自由な左手で地面の砂利を縋るように握りしめた。
「なん…っで…っ」
「何故…だと?敵を…っ、いたぶるのに理由など」
「あっ…!」
「貴様は、違うのか」
己の欲望を傷付いた穴から引き抜き、薄い肩を掴んでサルトビの体を返した。
圧迫感から解放されたサルトビの口から無意識の溜息が洩れる。
何故かそれにすら苛立って、ガルデンはサルトビの萎えた性器に爪を立てた。
「アアア…ッ!」
「私を忘れられるのか」
「ア…っ、ぐぅ…っ」
「どうした?私を殺すのではなかったのか」
痙攣する白い手が、ガルデンの腕を引き剥がそうと掴む。
「腐抜けたか。こんなにも辱められ、口惜しくはないのか?」
「…」
「忘れようとしているだけで、本当は一時も頭から離れたことはないのではないか?」
「…っ」
「まだとぼける気なら、言ってやろうか」
性器から手を離し、鼻先が触れそうな程近付いて、ガルデンは言葉の楔を穿った。
「お前の親を殺したのは私だ」
痛みと疲労に半ば朦朧としていたサルトビの眼が、徐々に見開かれる。
霞んでいた深緑色の瞳が、次々に様々な感情を見せた。
恐怖、哀しみ、困惑、そして、憎悪に揺らめく炎が、再び宿る。
それを見とめたガルデンの唇が、恍惚に歪んだ。
欲しいのは、歌声の様に心地良く胸に落ちる呪いの言葉。
自分しか映っていない彼の瞳。
彼の瞳にしか、私は映らない。
(私を許すなよ、サルトビ)
歌を忘れたカナリヤは象牙の舟に銀のかい
月夜の海に浮かべれば 忘れた歌を思い出す
Fin.
引用:童謡「かなりや」(詩・西条八十)
引用:童謡「かなりや」(詩・西条八十)