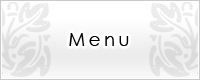35:人形
暗い森の中、雨音に交じり規則正しいギャロップの歩む音が響く。
馬上では黒いマントを被った痩躯の男が揺られていた。
整った唇から吐かれる息は雨に冷えた空気に白く変わり、長い睫毛に縁取られた切れ長の目は手にした羊皮紙に向けられている。
唐突に男が手綱を引き、ギャロップは短く鳴いて足を止める。
男は顔を上げ、ふ、と小さく溜息を吐いた。
「―ここは何処なんだ」
呟いても男は1人きり。答える者など居るはずもない。
「日が暮れてしまったではないか。役立たずめ!」
ばさりと投げ捨てられた地図は泥状になった地面に落ち、みるみるうちに雨に濡れていく。
男の名はガルデン。かつて全てを焼き払う暗黒騎士と恐れられ、そしてアースティアを救ったリュー使いの1人である。
迷子になった挙句、地図に八つ当たりをしている姿からは想像も付かぬ過去だ。
美貌と戦闘の才能に恵まれた彼には似合わぬ欠点だが、方向感覚が弱く、真っ直ぐ目的地に辿り着く方が珍しいという始末である。
そんな彼が1人で入り組んだ森を抜けようとしたのだから、この結果は当たり前とも言える。
「…そろそろ休むか」
どうやら完全に迷ってしまい、もう進んでいるのか戻っているのかも定かではない。
本日中に森を抜けるのが不可能と判断したガルデンはそう独りごちた。
しかし雨をしのげる場所でなければ、濡れた体を温め食事を作る火をおこすことが出来ない。
辺りを見渡すも滴を垂れる木ばかりで、その下で眠るにはあまりにも心許ない。
思わず二度目の溜息を吐いた瞬間、ギャロップが何かに弾かれた様に首を上げた。
「どうし…」
ギャロップの向いた方を窺おうと顔を上げると、甘い香りがかすかに雨の匂いに交じり、ガルデンの鼻腔をくすぐった。
どうせ目指す方向も分からない。ガルデンは誘われるようにそれを目指し、ギャロップの腹を軽く蹴った。
しばらく進むと岩壁にぶつかり、そこに小さな洞窟が口を開けていた。香りはここから漂っているようだ。
ギャロップを入り口脇の雨の当たらない木の下に繋いで荷物を下ろす。
中に入り、やっと雨から逃れられガルデンはひとまず安堵する。
マントを外し水滴を払う。服の下にも雨が染みて、体がすっかり冷え切っている。
思わず身震いすると、背中が暖かい空気が触れた。
振り返れば、洞窟の奥がぼんやりとオレンジに光っている。
誰かが焚き火をしているのだろうか。
ガルデンも火起こしの道具は持っているが、濡れた森から薪を調達するのは不可能に思えた。
甘い香りと暖かさに誘われ、ガルデンは洞窟の奥へと歩を進めた。
「…なんだこれは」
行き止まりにはドアがあった。
それは木彫りで細やかな花の彫刻が施され、取っ手などは金で出来ている。
その隙間からはちらちらと火の明かりと暖気、それに例の香りが漏れていた。
森の奥の洞窟のさらに最奥、この高級宿のような部屋はあまりにも不釣り合いだった。
「いらっしゃい。入って」
ふいに、ドアの中から女の声がした。
いぶかしんだガルデンだったが、ここで立ちすくんでいても仕方がない。
言われるがままドアを開けた。
瞬間、香でも焚いているのだろうか、甘い香りが強くなる。
「ようこそ」
中はまるで高級宿だった。
壁は無骨な岩ではなく平らで、アイボリーの壁紙が張り付けられていた。
家具は一見シンプルだが、よく見れば全て金や真鍮の細工がなされている品の良いものだった。
猫足のベッドの上には軽そうな羽毛布団が掛けられていて、誰かが眠っているらしく寝息に上下している。
「すまない。雨に降られて…」
「お客さんは歓迎よ。さあ火にあたって」
部屋の主らしい女は暖炉の近くの椅子を進めた。
萌黄色のロングワンピースとストールを身につけた、20代後半の美貌の女だった。
絹のような肌の顔を傾けると、長ぐ輝く赤毛が肩を滑る。
「あら、随分濡れたのね」
ガルデンの服から滴る水滴を見つけた女が立ち上がる。
床を汚したことをガルデンが謝ろうと口を開く前に、女が濡れた体をストール撫でるような仕草をした。
瞬間、ししどに濡れていたのが嘘のように服が乾いた。
「魔法使いなのか」
「ええ。何でも欲しいものを出してあげるわ」
女はテーブルからポットを取ると、ティーカップに注いでガルデンに差し出した。
ガルデンは腰を下ろし、カップを手に取る。
紅茶の温度も濃さも図ったように絶妙で、警戒しつつ一口含むと、それはガルデンが好む茶葉で入れたものだった。
「ここで暮らしているのか?」
「そうよ。この場所が好きなの。この部屋は楽園よ」
うっとりと女は部屋を見渡す。
「でもお客さんも好きよ。ゆっくりしていってね。みんなここを気に入ってくれるけど、すぐに行ってしまうの」
寂しげに眉を下げて紅茶を飲んだ後、髪を掻きあげながら女は顔を上げた。
「他に欲しいものは?」
妖艶に微笑む女の顔を見て、売春を持ち掛けられているのでは、とガルデンは推測した。
この地区では恐らく売春が禁止されていて、女は隠れてこんな森の奥でひっそりと宿を経営しているのだろう。
仕事で疲れた娼婦であれば、来客にも構わずベッドで眠っているのも不思議ではない。
「今は雨をしのげればそれで十分だ」
「まあ欲が無いのね」
大げさに肩を竦めた女は、カップを置いて立ちあがった。
ベッドの前まで進むと思わせぶりに振り返り、かすかに上下する掛け布団を撫でた。
「じゃあこれも要らなかったかしら」
女は悪戯っぽく笑うと、軽い羽毛布団を剥いだ。
そこに横になっている人物の姿に、ガルデンは驚きで目を見開いた。
壁際を向いて眠っているのは娼婦ではなく細みの少年で、深緑色の変わった装束と、鉛色の鉄兜を身に着けていた。
布団が無くなったことで目覚めたのか、少年は小さく呻きながら寝返りをうち、部屋の眩しさに腕で顔を隠した。
「サルトビか…?」
そう名を呼ばれても、少年は未だまどろんでいる様に反応がない。
女に軽く肩を叩かれてこちらに顔を向け、やっとガルデンを見た。
顔の作りは見知ったそれに違いはなかったが、肩と胸の鎧を外しぼんやりと自分を見やるその寝姿は、かつて命の遣り取りをした少年と同じ人間と思えぬほど無防備だった。
「お前は…何者だ?」
問いかけてもサルトビは無感動にガルデンに視線を投げかけたまま動こうとはしない。
「いやだ。貴方が一番よく知っているでしょう?」
代わりに言葉を返したのは女で、微笑みながらベッドに腰掛ける。
「お前は?」
「私?」
女が楽しげに笑う。
サルトビの両肩を優しく抱き、上体を起こしてやった。
「私は貴方よ」
無表情にガルデンを見つめるサルトビの華奢な肩を支えながら、女が悪戯っぽくそこに頭を乗せる。
「貴方の願望」
呆気にとられ立ちつくすガルデンをくすりと笑い、女はサルトビの頬に手を掛け、その覆面を下ろした。
抵抗無く肌を滑った深紫の布は少年の細い喉までもを晒す。
白い頬には一筋の切り傷が走り、それはたった今斬られたように鮮血が滲んでいた。
それは以前、ただ一度その素顔を見たときとまったく同じ姿で、思わずガルデンの体が強張る。
「私になりたい?」
女の声も心なしか遠い。
再び見たサルトビの白い肌、細い顎、薄く開かれた小さな唇、そして自分を見つめる澄んだ瞳に、ガルデンは射抜かれたように動けない。
「こうしたくはない?」
女はサルトビの顎に白魚のような指を静かに添えると、柔らかな仕草でその顔を自らの方に向ける。
ガルデンの手がピクリと動き、女は横目で笑いながらサルトビの唇に自分のそれを寄せる。
「待て」
ガルデンの声に女が動きを止める。
ゆっくりと振り向き柔和な笑みを浮かべ、サルトビの手を引きながら立ち上がる。
覚束ないながらも、サルトビが床に足をつく。
ガルデンが立った拍子に椅子が倒れ、その急いた様子に女がゆっくりと頷いた。
サルトビに近付くと、女はその体から手を離す。
ふらついたサルトビにガルデンは反射的に手を伸ばし、細い肢体を受け止めた。
思えばいつもこの少年とは刃を交わしてばかりで、こんな風に触れ合ったことはなかった。
見下ろすとサルトビと視線がぶつかり、白い顔が微笑んだ。
細められた眼も上がった口角も、初めて見る。
(こんな顔をしていたか?)
きつく睨む眼しか知らない。
あの日見た唇は苦痛に歪まれていた。
「ねえ?この子が欲しかったのでしょう?」
女がストールをなびかせながらガルデンの後ろに回る。
「ここに居ればいつまでもその子と遊んでいれるわ…。ね、3人で楽しく暮らしましょう」
広い背中に掌と額を当てしだれかかる。
ガルデンは微笑んだままのサルトビの顔へ手を伸ばす。
その背中で女は満足そうに笑う。
「見くびるな」
スラ、という音の方向に女が顔向けると、ガルデンの手に光る物を見つけ息を飲んだ。
「やめろッ!!」
女の制止を聞かずガルデンはサルトビの首元を押し突き飛ばすと、剣を胸に突き刺した。
刃に貫かれたサルトビの体からむせかえるほどの花の香りが噴き出し、鋭い断末魔がガルデンの耳をつんざく。
しかし苦しみ悶えたのは女の方で、サルトビは穏やかな笑みを浮かべたままガルデンの瞳を見つめていた。
「お…おノレェ…ッ!何てコト…何てことをォォッ!!」
女の腕がギチギチと怪音を立て、柔らかな肌は何本もの植物の蔓の集まりへ変わった。
蔓は痙攣しながらガルデンの首を目指し伸びる。
サルトビの頬の傷と、唇の間から赤い花弁が数枚零れ、ガルデンは目を瞑り突き立てた剣をえぐるように回した。
「アアッ!!アアアアアアアアァァァァ…ッ!!」
一層悲鳴が大きくなり、そして消えていった。
肩にかかった蔓が落ち、ガルデンは目を開ける。
眼の前にはサルトビではなく、大きな赤い花が剣に貫かれ枯れていた。
品の良い家具で形成されていた部屋はただの岩と枯れた蔓で埋められた洞窟に戻っている。
ガルデンが剣を引き抜くと蔓がずれ、絡みつかれたままのミイラ状の死体がごとりと揺れた。
「妖花か…」
甘い香りで人を誘い、幻術で獲物を惑わせその精気を吸う。
そういった魔物が居るとは聞いていた。
「案外つたない幻術だったな」
造形はともかく、所作や表情はサルトビとは似ても似つかないものだった。
本物のサルトビは頑なに素顔を隠し、意思のある瞳でガルデンを睨む。
(サルトビは、)
―この子が欲しかったのでしょう
「っ、」
妖花の言葉が脳裏に蘇り、ガルデンは剣を鞘に収めるとマントを翻し足早にその場を立ち去った。
(そんな筈がないだろう。奴は、奴と私は…)
苛立ったようにガルデンは頭を振った。
それでも、あの微笑が瞼に焼き付いたまま消えない。
Fin.