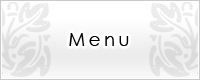衆合地獄で会いましょう
教師の朗々とした声と、ノートに鉛筆が擦れる音が響く教室。
その中で、学習机には不釣り合いな190cmの長身が一瞬強ばったことに、何人が気付いただろうか。
鹿児島学院は仏教系の高校なので、当然そういった授業がある。
蘇我と一緒がいいから、という理由で入学した九鬼は信仰心が薄く、僧侶になる予定もないため仏教学は真面目に聞いていない。
だが今日の授業テーマは「地獄について」という少々過激なもので、九鬼は好奇心からいつもよりほんの少し真剣に教師の話に耳を傾けていた。
そして何気なくめくった教科書に、自分が堕ちるであろう地獄を見付けたのだ。
それは、「衆合地獄の十六小地獄、多苦悩処」。
男と愛し合った男が堕ちる地獄である。
ノートもとらずにじっとそのページだけを見つめていると、チャイムが鳴り午前の授業が終わった。
ガタガタと椅子を鳴らし立つクラスメイトにつられるようにして、九鬼も教科書を閉じ立ち上がる。
九鬼もまさか本当に地獄というものがあるとは思っていない。
だが、そういう地獄があるということは、仏様はゲイがお嫌いであられるのだ。
仏がホモフォビアであろうがなかろうが九鬼には関係のないことだが、恋人の蘇我はそうもいかない。
蘇我は寺の息子で、将来仏に仕える身だ。
まるで恋人の親に交際を反対されているような絶望と、自分が蘇我の将来に暗雲を落としているのではないかという自責の念で肩を落としながら、九鬼はトボトボと学食へ向かった。
「どうした一平。腹でも壊したか」
言ってから蘇我は九鬼が手にしたカツ丼に目を落とし、大丈夫そうだなと続けた。
「オレだって感傷的になるときだってあるんだよ」
九鬼は心外だという風に唇を尖らせる。
それを見ながら蘇我はきつねうどんとおにぎりを九鬼の向かいの席に置き、座った。
「珍しいな。悩み事か?」
実直な目で見つめられ、九鬼は心情を吐露しようとして、言い淀んだ。
“ホモが堕ちる地獄を知って、ショックだ”、なんて、子どもっぽすぎるだろう。
「…さっきの仏教学で…」
「仏教学?勉強のことでお前が悩むなんて」
蘇我が驚愕に目を見開く。
「いや、勉強っつーか…地獄の話で」
そんなに驚かなくても、と思いつつ、実際授業とは関係ないことで気を揉んでいる九鬼は、長い指で割り箸を弄びながらもごもごと言葉を紡ぐ。
「地獄?…ああ、それならうちのクラスも昨日受けたぞ。なんだ、お前も案外繊細なところがあるな」
蘇我は目を細めて笑い、安堵して箸を割った。
「そうじゃなくってェ!」
短気な九鬼は、言葉を濁すのがもどかしくなり、高い上背をテーブルに乗り出して小声で告げる。
「その…。ホモが堕ちる地獄ってのがあって…」
うどんをすする途中で、蘇我の箸が止まった。
「生前にやった相手がいてさー…、抱こうとするとそいつの体が燃えて、焼かれるんだってさ…。なんつーか、仏教じゃオレたち日陰モンなんだなーって…」
言いながら九鬼は、まるで幼稚な発言に思えてきて、頭をガリガリと掻いた。
仏に反対されることが怖いのではなく、僧侶になる蘇我の足を引っ張ることになるのではないか、真面目な蘇我が仏の教えと自分との交際の狭間で苦しむのではないか、ということが怖いのだ。
しかし九鬼はそれをうまく説明出来ず、口を塞ぐようにカツ丼を頬張った。
蘇我はそれを見て自分もうどんをすすりあげ、黙って咀嚼する。
少しの間、二人の間に沈黙が訪れた。
九鬼は味噌汁をすすりながら、次に蘇我の口が開かれたとき、「それはいけないな、別れよう」と言われたらどうしようか、と内心穏やかではなかった。
蘇我は彫りの深い顔を僅かに思慮で歪めながら、じっと黙ってうどんを噛んでいる。
周囲の秩序を保ったざわめきが、二人を包んだ。
「思うんだが…」
うどんの汁を飲んだ蘇我が丼を下ろし、やっと言葉を発した。
九鬼が大きな体を緊張させる。
「死んだときはお互い爺さんだろうし、そういうことをしなければいいんじゃないか」
意志を持った眉の下の凛々しい瞳で真っ直ぐに見据えられ、九鬼は一瞬ぽかんと口を開けた。
「あー、うんそりゃそうかもしれねーけど…えっそういう問題?」
「そういう問題だろう」
解決だ、と続けて蘇我はまたうどんに手を付ける。
「そういうことが気になるんじゃなくってェ…うー、なんつえばいーか…。坊さんになるハジメの邪魔したくねぇの」
周囲を気にしながらも長い腕をもどかしく揺らし、無意味な身振り手振りを交えながら九鬼は必死に訴える。
「いつになく真面目だな」
「ハジメとのことはちゃんとしてぇんだよ」
真剣に、九鬼はそんな恥ずかしいことを言う。
九鬼は蘇我を愛することに、配慮はあっても一切の照れがない。
言われた蘇我の方が赤面して、思わず俯く。
「…一平、お前は目立つんだから大人しくしろ」
落ち着いて座っている蘇我に対し、九鬼は190cmの長身で上半身と長い腕を振り動かす九鬼は、嫌でも周囲の眼に入る。
いつものことだが、こんな会話をしているときには気になる。
それでも蘇我は俯きながら、九鬼の心配を取り除くために言葉を繋いだ。
「…それにな、昔の僧侶は女人禁制の生活していたから、小姓なんかと付き合うのが当たり前だったそうだ」
「えっ。てことは…」
九鬼が目を丸くしたのを見て、蘇我はくすりと笑う。
「大先輩方はうまくやっていたということだ」
それにならえばいいのだ、と言って蘇我はうどんをすすった。
虚を突かれて九鬼は上体をのけぞらせた。
「ハジメがそんなテキトーなことを言うなんて、意外だぜ」
「お前に対しては適度に手を抜くことにしたんだ」
ひでぇ、と情けない声を挙げる九鬼をちらりと見やって、蘇我はぽつりと続けた。
「…そうでないと身が持たないだろう。爺さんになるまで付き合うんだ」
九鬼は、またもやぽかんと口を開けるしかなかった。
うどんを持ち上げたまま、蘇我は「早く食わんと昼休みが終わるぞ」と話を逸らす。
「ハジメ」
照れ屋な恋人の精一杯のプロポーズが愛しくて、愛しくて、九鬼はまた身を乗り出して耳元で囁いた。
「勃つうちにいっぱいしなきゃな」
パチン、と乾いた音を立てて、蘇我の大きな手が九鬼の頭を叩いた。
「いてぇ」
「すぐにそういうことを…」
モゴモゴと小さく呟き、蘇我は横向きに座り直し、顔を背けておにぎりを頬張る。
「せいぜい他の地獄に堕ちないようにしろ」
その真っ赤な耳を見ながら、九鬼はくっくっと笑い出すのを堪えていた。
触れないのは少し寂しいけれど、二人一緒なら地獄も悪くはない。
九鬼は通り掛かった須佐見に不審がられるまで、ニヤニヤと不気味に笑いながらカツ丼と幸せを噛み締めた。
FIN.