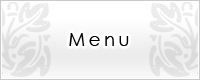95:死神
草木も眠る丑三つ時、森の奥深くに1人の老人が居た。
ここで夜を明かそうと、地面に腰を下ろし、静かに火の番をしている。
古びた白装束に身を包み、首から下げた長い数珠を、節くれだった指で弄んでいた。
傍らではギャロップが首を丸めて眠っている。
風一つなく、鳥や虫の気配も感じない。
薪が燃える音とギャロップの規則正しい寝息だけが聞こえている。
その静寂の中に微かな人の足音が混じった。
それは徐々に近づいて来るが、老人は興味を示さずただ揺れる火を見るともなく見ていた。
お互い沈黙を保ったまま、老人は動かず、歩く男は通り過ぎるかと思われた。
俯いた老人の眼にちらりと青い光が映りこみ、ぼんやりと皺だらけの顔を上げた。
数珠を弄る手が止まる。
歩く男は気にもかけず足を前に運ぶ。
「もし」
老人が掠れた声を出し、男は足を止めた。
男は全身を黒衣に包んでいたが、不思議と闇の中で姿が浮き上がっているように見える。
向き直った男は、恐ろしいほどの美男子だった。
甲冑とマントに包まれた体はすらりと細く、かたちの良い唇と通った鼻筋、輝くような銀の髪を持っていた。
何よりその美しさを際立たせていたのは、長い睫毛に縁取られた切れ長の眼だった。
老人を見下ろすその瞳は冷酷そうな硬質の光を湛えていた。
「私を呼んだのか」
「そうだ。その…つかぬことをお聞きするが…」
焚き火の灯りに照らされた老人の顔には、あきらかに恐怖の色が浮かんでいた。
「お主、人を殺めたことがあるな」
男は訝しげに眉を顰める。
髪と同じ、銀の眉の下の瞳に冷たさが増す。
「何故そんなことを訊く」
老人はゆっくりと右腕を挙げた。
人差し指だけを伸ばしたその手は小刻みに震えながら男の右肩の上の空間を指した。
「鬼火が…鬼火が憑いておる」
男は右をちらりと見やる。
そこにはただ暗い空気があるだけで、火など何処にも見当たらない。
「本当じゃ。儂は悪霊払いを生業にしている霊者なのだ。この世の者ではないものが視える」
「その鬼火とやらを払いたいと?そんな子供騙しの商売に…」
「とんでもない!」
老人は恐ろしげにぶるぶると首を横に振った。
怯えながら視線を男の右肩から左、そして頭上へと、何かを追うように彷徨わせる。
「お主に憑いておる者は、長い年月を掛け、恨みだけが凝縮された怨霊。儂は幾多の霊を払ってきたが、こんなにも強い怨念を持つものは初めてじゃ…」
「…では何故声を」
「儂の手には余るが、広いアースティアの何処かにその鬼火を払える霊者や僧侶がいるやも知れぬ。忠告と思って老いぼれの言葉を覚えておいて損はない…」
「…」
「病でないのに心臓が痛むことはないか?蜃気楼を見ることは?風もないのに火に襲われたことは?」
男の眉がぴくりと動いた。
ゆっくりと黒い手袋を外し、腕を捲ると、大きな火傷痕が現れる。
老人は一瞬息を呑み、大仰な溜息を吐いた。
「やはり…」
「急ぐ旅ではない。暇つぶしに話に付き合ってやろう」
ばさりとマントを後ろに払い、男は焚き火を挟んで老人の向かいに腰を下ろした。
「まず最初の質問に答えてやろう。"人を殺めたか"だったな。答えは"数え切れぬほど"だ」
老人は畏怖の眼で男を見る。
男はその恐怖の色を見つけると愉快そうに唇を歪めた。
「そうか…。しかし、その鬼火は一つの魂で出来ておる。特別酷い恨みを買った覚えは…」
「特別…ふ、一人、居る」
呟くと、男は思い出に浸るように一度薄いまぶたを閉じた。
再びゆっくりと開かれた眼は爛々と輝いていて、老人は怖気をふるう。
「100年も前の話だ――」
男は淡々と語り始めた。
力を求めて数多の村を焼いたこと、忠実な腹心と思っていた老婆に裏切られ、殺したこと。
目的を失い戦争から手を引いたこと。
結果、それまでの敵と戦う必要が無くなり、退屈を感じたこと。
「その時、敵側にも一人、戦争から手を引いた者がいた。焼いたある村の生き残りの少年だ」
老人の背に冷たい汗が流れる。
「その、少年が…」
「おそらくな。仲間に背を向け、私を追って来たのだ」
「そしてお主は、その少年までもを…」
「ああ。以前斬ったはずの腕を、また生意気にも付けていたので、再び斬った」
まるで世間話のように、男は鬼畜の所業を告白する。
焚き火が揺れるのを見つめながら話す男の涼しげな眼に、肌が粟立つ。
「すると『片腕でも刀は持てる』と言うので、もう片方も斬った」
「それでも私に向かってきたので、両脚の腱を斬った」
「『その体でどうやって私を殺す』と問うと『首だけになっても、お前を噛み殺す』と言うので、ならば、と首を落としたら…」
霊者の歯がガチガチと鳴っていた。
炎に照らされた男の眼は言葉を紡ぐたびに冷酷な光を増し、唇の片側を釣り上げ笑みさえ浮かべる。
「死んでしまった」
パチパチという薪が小さく爆ぜる音だけが響く。
霊者は男の視線の進路をなぞるように炎に目を向け、震える手を握った。
「…もう」
やっとの思いで霊者の喉から絞り出した声は滑稽なほど乾いていた。
ごくりと唾を飲み込む音は炎が空気を燃やす音に掻き消される。
「もうその鬼火には人だった頃の記憶は無いだろう。お主への恨みの理由も忘れて…」
橙色だった焚き火は男が話し始めてから青く変わり、薪を全て燃やしつくす勢いで徐々に大きくなっていく。
霊者その炎から見開いた眼を離せぬまま、額の脂汗を拭う。
「あるのはお主の命への執着のみ…」
「…随分律儀だな」
男は眼を細めて炎を見る。
眠っていたギャロップが弾かれるように首を上げ、炎に向かって威嚇に喉を鳴らす。
そして旧友に呼び掛けるように、整った唇が霊者の知らぬ名を呟いた。
「サルトビ」
瞬間、焚き火は青い火柱となり男を襲う。
霊者が腰を抜かして悲鳴を上げた。
飛び起きたギャロップがギャアと甲高く声を上げ羽を逆立てる。
男は素早く立ち上がるとマントを翻し火を遮った。
その風に煽られた火柱は勢いを無くし、縮まるように焚き火の上に収まる。
それでも、ほとんど消し炭となった薪の上で火は消えることなく、男の隙を狙うかのように一定の大きさを保ったまま揺れている。
しばし呆然としていた老人だが、ギャロップが繋いだ縄を引き千切らんばかりに暴れているのに気付き、震える膝をなんとか宥めて立ち上がる。
縄をしっかりと握り、どうどうと声を掛けながら毛並みを撫でてやると、ギャロップは徐々に落ち着きを取り戻し、黙ってゆっくりと膝を折った。
男はそんな老人とギャロップを尻目にマントの灰を払うと、踵を返し立ち去ろうとした。
小石を踏む音に老人が振り向き、振り絞るような声を出す。
「いつかお主は鬼火に焼かれ、それと共に…地獄へ堕ちる」
男は一時足を止め、横顔で答えた。
唇は笑いを堪え切れずに歪んでいた。
「それも一興」
男は来た方向とは逆に歩みだす。
その後を追うように消し炭から青い火が浮かび上がり、焚き火の灯りを亡くした森は暗い静寂に包まれる。
燃える魂が揺れながら黒い後ろ姿を照らし、徐々に遠のくのを、老人はただ見送ることしか出来なかった。
Fin.