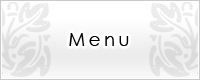48:刻印
木々の葉が光に透ける晴れた森、小鳥の囀りに混じり枝の揺れる音が規則的に鳴っていた。
よく見れば枝から枝、樹から樹へ飛び移る影がある。
それは一人の少年で、驚異的な身の軽さとスピードを持って、下界を見渡しながら進む。
目的を持って進むスピードに相反して、窺う眼には躊躇の色が見え隠れしていた。
ふいに、少年の足が止まる。
じっと見つめる視線の先には、黒衣に身を包んだ銀髪の男。
少年は躊躇う喉に息を吸い、一拍の後男の名を呼んだ。
「…ここにいたか、ガルデン」
痩躯の少年が樹から降り立つ。
振り向いた男はほんの僅か、頬を緩めた。
逢瀬の約束を交わした訳ではなかった。
気軽に会える仲でもない。
それだのに別段驚かずに受け入れるガルデンに、すべてを見透かされているようでサルトビは居心地悪く体を揺する。
「何か用か」
薄く笑みさえ浮かべたガルデンに、努めて冷静にサルトビは答える。
「頭主になるんだ」
意外な言葉に意図が掴めず、ガルデンは不思議そうに眉をひそめる。
「今の頭主様の娘と結婚すんだよ」
続けられたその台詞に、ガルデンの指がぴくりと跳ねた。
「頭主は里を守るのが仕事だ。今までみてぇに簡単に旅に出れねえ」
「…別れを、告げに来たのか」
「ついでだからな」
「何のだ」
「アデュー達に言いに行った…」
律義にこんなことを言いに来る必要はないはずだった。
だが、里に用意された居場所に収まるには、ガルデンへの感情を清算する必要がある、とサルトビは考えていた。
婚約者であるイオリや、現頭主のモモチは「忘れていい」と言う。
私たちは忘れて前を向く。お前ももう苦しむな、と。
それが出来るなら、最初から爆裂丸を盗み里を抜けなどしなかった。
思いつめて黙るサルトビに、ガルデンは細く溜息を吐いた。
「成程。あの時の軽口は別れの準備という訳か」
「なんのことだよ」
「言っただろう"仲間"などと…」
―お前もやっぱり仲間だったんだな。
カイオリスの戦いの前、サルトビは確かにそう発言した。
それは自分へ言い聞かせるためのものではなかったか。
「私は貴様の仲間などではない。他の奴らと同じ位置に落とし込んで、逃げるな」
「逃げ、てなんか…」
やはり、見透かされている。
反論出来ずに言葉に詰まるサルトビに、ガルデンはゆっくりと近付く。
反射的にサルトビは一歩後ずさった。
「私を殺せないなら、逃げるな」
その言葉に、サルトビは金縛りにあったように動けなくなる。
立ち尽くすサルトビに、ガルデンは一歩、一歩と草を踏む。
「別の道を行くのは当然のことだ。ただ、貴様は…」
手を伸ばせば触れられる距離まで近づき、ガルデンは右手をゆっくりと上げる。
「ずっと私を見ていろ」
青い手袋が視界を遮った。
勘づいたサルトビが身を引く前に、ガルデンが短い呪文を唱え、その掌から閃光が走る。
「アッ」
瞬間、右目に激痛を感じサルトビは顔を押さえ体を折る。
余りの痛みに眼が開かない。
傷付けられた右目からぼろぼろと涙がこぼれおちる。
「くそっ…!なに、しやがった…」
ガルデンは屈み込み両手でサルトビの顔を包み上を向かせた。
「呪いだ」
眼を押さえるサルトビの手を外し、とめどなく涙が溢れる瞼に唇を軽く当てると、呪文らしきものを囁く。
それが済むとマスクをずらし、唇をサルトビのそれに重ねた。
涙に濡れたガルデンの唇は触れた瞬間冷たく、塩の味がした。
体温を感じた刹那それは離れ、撫でるような動作で青い手袋がマスクを直す。
「さらばだ、サルトビ」
笑いを含みつつ微かに震える奇妙な声色で別れを告げ、気配が離れた。
必死に眼を開けたが、後ろ姿は涙にぼやけていた。
サルトビは痛む眼を庇いながら転げるようにその場を後にした。
しかし意外にもすぐに痛みは引き、半トキ後に見付けた泉に顔を映すと、充血も無く綺麗なものだった。
ひとまず失明を免れたことに胸を撫で下ろし、涙の跡を洗う。
水を拭い安堵に空を仰ぐと、晴天の中に銀の点がゆらりと流れた。
「飛蚊症だね」
里に戻って眼を診せた医者はそう診断し、聞き慣れない響きをサルトビは口の中で小さく反芻した。
ガルデンに眼を傷付けられてから、銀色の点が見えるようになった。
点はサルトビの視界の中で眠るように静止していると思えばふらふらと彷徨い、時には素早く走り存在を主張する。
眼球の傷なら仕方がない。
しかし、その動きは生きているように思えた。
「なにさ、ひぶんしょうって」
隣で診察の様子を見守っていたイオリが不安気に首をかしげた。
「よくあるものだよ。視界の中に白っぽいゴミが映る症状のこと。戦ってるときに目をぶつけたりしただろう?」
「…そうかもな」
「打撲が原因でなることが多い症状だ。あとは老化とかね」
「老化だって。あんたもいよいよ隠居かねぇ」
鈴のような声で笑う婚約者に、じじい扱いすんな、とサルトビは声を荒げた。
その様子を微笑ましく横目で見ながら中年の医師は紙にサルトビの症状を記入する。
「視界にゴミが映るだけで、戦いにも支障はないよ。でも頭主になれば外に出なくたっていいからねぇ」
「そうそ。里で大人しくしてな、頭主様」
「お前なぁ…」
「ははは、おっと」
少し開いた窓から風が吹き込み、医師は慌てて書きかけの書類を押さえた。
「しかし、あの泣き虫坊主が頭主になるとはねぇ…。いやぁ歳をとった訳だ」
医師はふくよかな体を揺らしながら立ちあがり、窓を閉める。
作務衣から伸びるふくらはぎの古い火傷痕を、サルトビと銀の点が見た。
「それで、これは治るのかよ」
視線を移しても、銀の点はふらりと視界の端の火傷痕の辺りに移動し、立ちつくすようにそこで止まった。
(何驚いてんだよ。お前が焼いたんだろ)
業火の中で嗤う黒いリュー、そして母を呼んで泣いた男の姿が同時に思い浮かんだ。
医師は銀の点の視線に気付くはずもなく、苦笑を浮かべて告げた。
「飛蚊症ってのはね、治らないんだ。鬱陶しいだろうけど、一生付き合っていくしかないね」
ほとんどあばら屋と言っていい診療所をイオリと二人後にし、モモチ邸へ戻った。
故郷のアスカジを焼かれて間もなく里を抜けたサルトビには家が無く、正式な婚姻はまだであるが、この屋敷に住んでいる。
質素であるが広い屋敷には未だ慣れず、イオリが茶を入れている間、囲炉裏端であぐらを掻いてじっと灰を見つめていた。
その視界の中には変わらず銀の点があり、それはもの珍しそうにふらふらと彷徨っている。
(あの時、)
眼を呪われているとき、口付けをされているとき、何故ガルデンを刺さなかったのか。
眼が開かなくても、触れ合っていた彼の心臓の位置くらいは解った。
しかし、あの時はそんなことは思い付きもしなかったのだ。
ただ、眼の痛みと、頬に触れる掌が震えていることが気になっていた。
「ごめんよ、正直言ってあたい、ちょっと安心してる」
ふいに上げられた高い声に、思考の底から意識が戻される。
視線を隣に投げると、イオリが困ったような、思い詰めた表情で茶をサルトビの前に置いた。
「何がだよ」
言いづらそうに顔を伏せるイオリを、サルトビと銀の点が見る。
「あんたがすっかり元気だったらさ、そのうち此処が退屈になってまた外を飛び回りそうで…」
「だとしても、戻ってくるに決まってんだろ」
「あんたはそのつもりでいるだろうけど、ね…」
言い淀み、暫しの沈黙の後、イオリはサルトビに向き直って笑う。
「あたい、やな嫁だね。亭主の病気を喜ぶなんてさ」
イオリが、そんなことを考えていたなんて知らなかった。
(こいつにも、見透かされてやがる)
「行かねぇよ、馬鹿」
躊躇いがちに腕を伸ばすと、胸に細い体が飛び込んできた。
驚きながらその肩に触れれば、背中に回された腕に力が入る。
視線を外しながら耳を赤く染めるこの少女を、愛しいと思う。
「イオリ」
呼ばれて少女が顔を上げる。
ふらふらと動く銀の点越しに、少女が照れ臭そうに笑うのを見る。
「キスしてもいい?」
口の中に涙の味が蘇り、一瞬体が強張る。
動揺を悟られないよう無表情でマスクをずらせば、頬を掠める手袋越しの指の感触に、またあの男を思いだす。
イオリが頬を染めて顔を寄せ、ゆっくりと瞼を閉じる。
銀の点は視界の中央で小さく震えていた。
眼を閉じても暗闇の中でそれは凛として光る。
きつく瞼を瞑って婚約者と唇を重ねると、銀の点が泣いている様に見えた。
Fin.