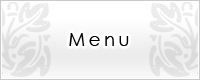27:エンドレス
「あれだけまだ咲いてんな」
窓枠に手を掛けサルトビが言った。
ガルデンは手にした本から顔を上げてサルトビの視線をたぐる。
そこには白い花が一輪風に揺れていた。
「昨日開いたばかりだろう」
「だから昨日散るはずなんだよ」
振り返ったサルトビはガルデンの不思議そうな顔を見ると愉快そうに笑った。
「あれは午時葵って花でな。一日花っつーか半日花っつーのか…とにかく数時間しか開花しねぇんだよ」
「あれだけが…」
「まあ俺も詳しくねぇからな。明日にはあれも散るんだろうよ」
サルトビは器用にガルデンから見えない角度で覆面をずらし、コーヒーを一口飲む。
「アデューたちは結婚を決めたそうだ」
唐突に話が転換し、ガルデンは虚を付かれて目を丸くしながら、成程、と今彼が仇と歓談している理由を察した。
邪竜族を討ってから3年、旅を続けていたアデュー一行とガルデンが再会したのは全くの偶然だった。
せっかくだから、と同行することを勧めたアデューの無邪気さをサルトビが非難しなかったのは、旅の終わりが近いと知っていたからなのだ。
「そうか。それは、目出度い」
「買出しから戻ってきたら祝福してやれよ。色ボケした顔で喜ぶぞ」
笑うサルトビにガルデンも曖昧に微笑する。
「俺もいつまでもフラフラしてられねぇな」
ぽつりと呟かれた言葉にガルデンの頬が強張る。
「…村に戻るのか」
「まだ行かねぇけどよ」
サルトビは外を向いたまま答える。
「俺ももう、遊びまわる年じゃねぇし…」
「まだたった18年しか生きていないのにな」
ガルデンは本を置いて立ち上がり、サルトビに近付く。
「人の時は私たちに比べて早すぎる。お前たちは私に気の遠くなる程の孤独を置いて逝ってしまう」
「何、言…って…」
語尾は不明瞭に消え入り、サルトビの手からカップが滑り落ち、床に陶器の破片と黒い液体が撒き散らされた。
膝から崩れる体を支え、抱きとめる。
「時が止まればいいと思う」
気を失って腕の中で眠るサルトビにそう囁き、ガルデンは窓を閉め二人を閉じ込めた。
傾き出した陽に照らされながら、ガルデンは風に揺れる一輪の花を見ていた。
枯れない一日花。
数時間のはずの寿命を数十年に延ばした己の魔法の力に、頬が自然と緩む。
「アンタに花を愛でる趣味があるなんてな」
振り向けばサルトビが訝しげな表情を浮かべて立っていた。
「どうした」
「アデュー達戻って来ねぇから、様子見に行って来る」
「いや、私が行こう」
この会話も何度目だろう。
こんな平凡な日常を二人きりで送れる事実にまた微笑を浮かべてしまい、それを見るサルトビの不可解な表情も見慣れた。
サルトビは不老の魔法を掛けられた60年前の8月9日を繰り返している。
宿屋だった此処を魔法を掛けた日の朝買い取り、二人の家にした。
起床し、食事を摂り、それぞれ時間を潰し、偶に会話を交わし、食事を摂り、時折外に出たがるサルトビを言いくるめ買い出しに行き、食事を摂り、風呂に入り、眠る。
朝になればサルトビは前日のことは忘れ、また同じことを繰り返す。
「アデュー達に会えなかったら食料でも買ってくる。入れ違いになるかもしれん。お前は此処にいろ」
「そうか…じゃあ、頼んだぜ」
立ち上がったガルデンのマントが揺れるのを見て、サルトビは何気なく付け加えた。
「今日は8月にしては涼しいな」
ガルデンはそれには答えずに、サルトビが建物の方に戻って歩き出したのを確認すると、外へと向かった。
ゲートを開くと冷たい風と雪がガルデンの体を襲う。
寒さに震えてマントの前を合わせる。
庭を囲う柵を境界に結界が張ってあり、毎年夏が終わる前にそこに魔法を足す。
サルトビの目を誤魔化すため結界の内側に夏の風景が映る魔法だ。
町とこの家のまでの道中には惑わしの魔法が掛けられ、誰も辿り着けない。
今はガルデン以外、蟻一匹、雪一粒、そしてサルトビも入ることも出ることも出来ない。
変わらない二人と一輪の花、庭に閉じ込められた植物と虫達の子孫が命を繰り返す、さしずめビオトープのような空間になっている。
完全に陽が落ちた頃に森を抜けたガルデンは、街の様子が普段と違うことに気付いた。
全ての店が閉まり、街灯は消されていた。
民家にも人の気配はなく、代わりに街の中心にある広場に蝋燭の灯りがいくつも揺れ、合唱が低く聞こえてきた。
不思議に思いながらガルデンはそちらに足を向けた。
合唱はガルデンの知らない歌であったが、讃美歌や聖歌の類に思えた。
その歌声に啜り泣きが混じっているのが聞こえ、誰かが死んだのだと分かった。
市長か誰かだろうか、と考え役所の方に視線を投げると、パフリシア国旗が旗竿の半分までしか上がっていない。
雪の向こうの揺れる半旗に、ガルデンの胸がざわついた。
ゆっくりとした足取りが早足に変わり、気付けば全速力で走り出していた。
広場には街中の人が集まっていた。
それなのに、露天や旅人向けの大道芸人達で賑わっている普段とは比べ物にならぬほど沈んだ空気が漂っていた。
中心の舞台の上には黒い衣装に身を包んだ聖歌隊が蝋燭を手に歌い、集まった皆が合唱している。
全員揃って悲痛な面持ちをしており、中には声を上げて泣いているものもいた。
聖歌隊の頭上に花で飾られた大きな写真が掲げられていた。
柔和に微笑み、威厳を感じさせる老人の写真だった。
ガルデンには知らない老人だった。しかし、その瞳はかつて自分を救った少年のそれに酷似しており、ガルデンの足を止めた。
合唱が止み、町長らしき中年の男が壇上に現れる。
語りだした言葉はガルデンの耳に入らなかったが、最後に張り上げられた声は、ガルデンを刺した。
「偉大なアデュー・パフリシア国王に、黙祷」
全員が目を瞑り、啜り泣き肩を震わせた。
ただガルデンだけが目を見開いたまま、そこに立ちつくしていた。
どうやって帰ったのかも覚えていない。
しかし、60年、何百回と歩いた道だ。目を瞑っても歩ける。
いつかアデューが死ぬことなど、ずっと分かっていたはずだった。
この道を選んだ以上、自分が葬儀に出れないことも、サルトビに親友の死に顔を見せてやれぬことも、分かっていた。
ガルデンは、サルトビの人生を奪った。
そんな自分に、アデューの死を悼む権利があるのか、傷付くことが許されるのか、思考が捻れたままドアを開け、転がるように室内へ入った。
「どうしたんだよ」
尋常でない様子にサルトビが眼を丸くして椅子から立ち上がる。
視線がマントに付いた溶けた雪を捕らえ、晴れていたはずの窓の外へ移動する。
「いや…なんでもない」
強張った顔でそう答え、ガルデンは窓の日よけを下ろした。
その様子にサルトビは深く尋ねることが出来ず、話題を変えた。
「そ、うか…。そんで、アデュー達は見なかったのか」
びくんとガルデンの肩が跳ねる。
顔を上げれば訝しげなサルトビの視線とぶつかり、勝手に言葉がガルデンの唇から零れた。
「しんだよ」
飲み込めなかった感情が溢れる。
「アデューは死んだ」
「は…?何言って…」
「老衰で死んだのだ」
「おい、たちの悪ぃ冗談…老衰?」
「今は冬だ」
ガルデンは窓を開け、空に手を伸ばし小さく呪文らしきものを唱えた。
ゆらりと夜空が歪み、重い雲と雪景色に変わる。
「そして、此処に来てから60年経つ。60年前お前に魔法をかけた」
絶句するサルトビにガルデンは告白を続ける。
「お前の時間を止める魔法だ。お前は60年前の8月9日を繰り返してる。眠れば"8月9日"にあったことは忘れ、また新たな"8月9日"が始まる」
困惑するサルトビに振り返り、さらに言葉を紡ぐ。
「"昨日"私がコーヒーを淹れたろう?」
はっとサルトビが目を見開く。
「睡眠薬を混ぜて眠らせ、その後に魔法を…」
サルトビは駆け出しドアを開け外に飛び出した。
横をすり抜けた風がひどく冷たい。
「ッ、サルトビ」
搾り出すように名を呼び、後を追う。
閉じ込められた少年はゲートに張られた結界に阻まれ、見えない壁を叩いていた。
「サルトビ!」
「離せ…っ!」
クナイを振りかぶる手を掴んだが、無謀だと分かってなお細い体は開放されようともがく。
「なん…でだよ!60年って…、死…っ」
後ろから、暴れる腕ごと抱きすくめた。
「行くなサルトビ。行くな…」
逃れようともがいていたサルトビの動きが徐々に弱まり、わめき声が泣き声に変わった。
60年も共に過ごしているのに、泣いているのを見るのは初めてだった。
サルトビは暴れる気力を無くし、膝を付いて声を上げて泣いた。
ガルデンはその震える体をただきつく抱きしめていた。
小鳥の鳴き声で目を覚ますと、陽はすでに上りきっていた。
ガルデンはサルトビをベッドの上で正面から抱きしめる形で眠っていたことに気付き、腕に込める力を強める。
どうやってなだめたのかもよく覚えていない。
サルトビの目元は泣き腫らして赤く、頬には涙の跡が幾筋も走り、覆面に染み込んでいた。
この瞼が開いたら、昨日のことは忘れられている。
真相を告げたのは、そんな甘えがあったからかもしれない。
懺悔のつもりだったのか、それとも溢れる感情を吐き出したかっただけだったのか。
どうせ彼は忘れるのだから、自分の哀しみをぶつけても構わないだろうと、そんな傲慢な想いが無かったと言えば嘘になる。
サルトビを閉じ込め、全てを奪い、自分の物にした。
そのことに胸を裂かれる罪悪感を感じているのに、結界を解く気にはならなかった。
それに、今魔法を解けば、無理に成長を止められた体と時の流れる世界との軋轢で、老いる前に肉体と魂が崩壊してしまう。
後悔しても、もう後戻りは出来ない。
嘘に嘘を塗り重ね、共に60年前の8月9日を繰り返し、数百年後ガルデンの顔に皺が出来るまで、否、出来ても、共に過ごすしかないのだ。
「ん…」
暗い決意を新たにするガルデンの思考は、小さな吐息に遮られた。
サルトビの顔を覗き込むと、未だ夢現の深緑の瞳と眼が合った。
「起きたか…」
無理に微笑んで見せたが、上手く笑えているか自信が無い。
サルトビはまだ眠そうにぼんやりとした眼でガルデンを見ている。
この眼が徐々に覚醒して、ガルデンにベッドで抱きしめられていると気付き、顔を赤くして跳ね起きるだろう。
『なにしてんだ、気色悪い』とでも悪態をついて、また同じ一日を過ごすのだ。
ガルデンが望んだ終わらない一日を、サルトビが失った限りある一生を。
もう一度笑ってみると、サルトビは覚醒した眼でベッドから跳ね降り、クナイを構えた。
それほどまでか、と苦笑するガルデンに、サルトビは警戒した顔で言う。
「あんた…誰だ?」
サルトビは、何もかもを忘れていた。
体が習慣として覚えているのか、武器の持ち方や覆面をしたままの生活は変わらなかったが、自分の名も分からなくなっていた。
余りに強い衝撃を心に受け、魂が不安定になってしまったのだろうと、ガルデンは推測した。
だが、ガルデンにはどうすることも出来なかった。
ガルデンが得意とする魔法は攻撃魔法で、不老の魔法は使えてもこんな状況に対応する術は知らなかった。
重量の増えた罪悪感を抱え、サルトビの世話をする8月9日が始まった。
ガルデンは記憶を失って倒れていたサルトビを拾った、と説明した。
仲間だと言うのは余りに厚かましく思えたし、仇だと言って再び苦しませたくは無かった。
最初は警戒するものの、敵意が無いことを察すると徐々に心を許し、夕飯の頃には笑顔を見せるようになる。
しかし、夜眠り朝起きるとその記憶は失われ、「誰だ」という問いが繰り返される。
毎日「誰だ」と問われ、偽りの関係を教えていると、自分が何者だったのか見失いそうになる。
そして、必死に記憶を取り戻そうとダイニングで頭を抱えるサルトビを見ながら、それを心地いいと感じる自分を見付ける。
サルトビの仇ではない自分。
簡単に手放せるほど軽い罪ではないと思いながら、憎まれず、ただ傍に居れるのは楽だった。
始めに異変が現れたのは料理だった。
世話になるから、と食事はサルトビが作ることが多い。
元々嫌いではないのだろう、大抵のものは標準以上の出来で作ってみせた。
素直に旨いと褒めれば、そうだろうと答え少しおどけて照れる。
「仇」には見せないそんな表情に、ガルデンは胸を痛めながらも幸せを感じていた。
しかし、やっと記憶の無い彼と過ごすことに慣れた頃、その味が変わった。
「…あんま旨くねぇか?」
一口食べて固まったガルデンに、申し訳なさそうにサルトビが尋ねる。
「いや、そんなことはないぞ…」
無理に笑って見せ、もう一度口に運ぶ。
不味いという以前に、何の味付けも施されていなかった。
「俺はもう食べたから、ゆっくり食えよ」
そう言って笑い、調理器具を洗うためにサルトビは立ち上がった。
正常な味覚なら、気付かないはずのない間違い。
彼は、ゆっくりと壊れていた。
次に忘れたのは武器の持ち方だった。
クナイや煙玉などの武器をテーブルに並べ、サルトビは首を捻った。
ガルデンは動揺を悟られないように本に眼を落としたまま、戦いを忘れたサルトビを見ないようにした。
「なぁ、これ、なんだと思う」
顔を上げると、サルトビが不思議そうに、最も大切な武器をこちらにかざしている。
カード状のそれに埋め込まれた青い球がきらりと、何か言いたげに光った。
「…それは、ミストロットという」
震える喉が、勝手に言葉を吐いた。
初めて聞いた、という風にサルトビは首を傾げる。
「それで、リューを、リューと呼ばれる巨人を召喚し、戦うのだ」
「ふぅん。巨人なんか呼んで、誰と戦うんだ?」
「それは、邪竜族と…」
言いかけた言葉を取り消し、ごく、と唾を飲み言い直した。
「お前のリューは、私と戦う為にあるのだ」
ぽかんと、サルトビはミストロットをいじる手を止め、ガルデンを見た。
「サルトビ、私はお前の故郷の仇だ」
続けられた台詞に、サルトビはミストロットを持つ手を下げた。
「そう、言われてもな…」
困惑し、ガルデンから眼を逸らす。
「なんにも、覚えてねぇからなぁ…」
重苦しい沈黙が続いた。
今すぐその手にクナイを握らせ、自分の喉を?っ切りたい。
ガルデンはそんな衝動に押しつぶされ、泣き出しそうだった。
「ちょっと、部屋に行くわ」
気まずそうに立ち上がり、サルトビは広げた武器をそのままに部屋を立ち去った。
置いて行かれたミストロットが、偽りの夏の光を跳ね返している。
「私を殺してもいいのだ…」
苦く、呟いた台詞はサルトビには届かなかった。
何者でも無いのが心地よい?
傍に居れればいい?
そんな考えは陳腐な慰めだ。
自分の心を守る為の偽りの感情だ。
本当は傍に居れなくても良かったのだ。
ただ自分を見てくれれば、この名を、覚えていてくれれば、良かった。
「今更、私は…」
ガルデンは誰もいない部屋で、虚しく拳を握った。
ガルデンの後悔を嗤うように、サルトビの崩壊は進んでいった。
語彙が徐々に減り、包丁の持ち方を忘れ、甲冑と兜を身に着けることを忘れた。
食事を摂ることを忘れることもあった。
料理を作って差し出しても食べる気配を見せず、手伝おうとしても覆面を取ることを嫌がるためそれも出来ず、細い体はますます痩せた。
体内時計も狂ってしまったらしく、最近は真夜中にうろついている。
肉体と魂は密接に繋がっている。
不規則な生活で体力が低下すると、魂の磨耗が進み、忘却が早くなると考え、ガルデンは睡眠薬を飲ませることを決めた。
彼に魔法を掛けてから、70年が経過していた。
夕食後、ガルデンは錠剤を砕きながらあの日のことを思い出していた。
今日のようにコーヒーを作りながら、胸の内でアデューに真っ当な道を選ばないことを謝っていた。
そして、サルトビを手に入れる喜びを噛み締めていた。
(しかし、矢張り間違いだった)
手に入れることは出来なかった。
楽園だと思った結界の中は砂で出来た城で、目の前でゆっくりと崩れていく。
この手に残ったのは永遠等無いという、分かりきった、残酷な事実だけだった。
砕いた白い粉を黒い液体に混ぜ、重苦しい気持ちを抱えサルトビの寝室へ向かった。
「サルトビ、少しいいか」
ノックをし、声を掛けても返事が無い。
今日は寝ているのかとも思ったがそれにしては時間が早い。
「入るぞ」
断ってドアを開けると、サルトビは起きていた。
ベッドの上にあぐらを掻いて座り、沈む夕日を見ていた。
赤い光に染まる白い頬と、ベッドの下に落ちている覆面を見て、ガルデンはカップを取り落としそうになる。
「サルトビ」
声が震えないよう気をつけて再び名を呼ぶ。
振り向いたサルトビの手に、暖かなカップを持たせた。
「コーヒーを淹れたんだ。飲んでくれないか」
言われるがままカップに顔を寄せたサルトビは、液体に唇が触れる前に眉をしかめた。
「嫌だ…薬くさい」
そう言ってカップを突き帰す。
落胆し、ガルデンは受け取ったカップをサイドテーブルに置く。
流石に忍びは敏感だと溜息を吐いて、ふとガルデンは気が付いた。
「今…なんと言った?」
―薬くさい。
体の震えを止められない。
あの日、不老の魔法を掛ける為に飲ませたのも、これと同じ薬、同じコーヒーだった。
ここまで耄碌しても香りの強いコーヒーの中から薬の匂いを嗅ぎ分けたのだ。
一流の忍びだった70年前のあの日だって。
「お前は…気付い、て…」
ガルデンはベッドの脇に崩れ落ちた。
何の薬なのか、ガルデンが自分をどうしようとしているのか分からぬまま、サルトビは自分の身を差し出したのだ。
「死ぬかもしれないと、思ったろう。それでも、私の気が済むならと、私の為ならと、思ってくれたのか、サルトビ」
嗚咽に混じり紡がれる台詞は、今のサルトビには理解出来なかったかもしれない。
それでも、細い指はベッドに額を押し付けて泣くガルデンの髪を撫でた。
ガルデンは涙に濡れた顔を上げ、サルトビを見た。
サルトビは、子供の様な眼でガルデンを見ていた。
「ずっと、縛り付けてすまなかった。有難う」
ポケットから睡眠薬の瓶を取り出し、中身を掌に空ける。
数粒口に含み、サルトビに口付ける。
舌で薬を押し込むと、サルトビは抵抗することなく受け止める。
唇を離し同様にコーヒーを流し込むと、細い喉が錠剤を飲み込んだ。
それをコーヒーが無くなるまで繰り返し、最後は空の口で長いキスをした。
顔を離すと、サルトビは既にまどろんでいた。
「おやすみ」
涙に濡れた顔でそう言うと、サルトビは微かに笑った。
「おやすみ、ガルデン」
それは、忘れられたはずの名だった。
深い眠りに引き込まれたサルトビの体を、ガルデンはきつく抱いた。
サルトビの眠りを妨げ無い様に、声を殺して泣きながら、寝息が聞こえなくなって、体温がすべてシーツに染み込んでも、構わずにただ抱いていた。
太陽が遠い稜線から顔を出し、小鳥が鳴いて、やっと痺れた腕を緩め、少年の躯を抱き上げ、庭に出た。
柔らかな日差しは、サルトビの旅立ちを祝福しているようにガルデンには思えた。
優しく細い体を芝生の上に下ろすと、空に手をかざし呪文を唱えた。
結界が解かれ、2羽の小鳥が庭に舞い込んだ。
そしてゆっくりと花壇に近付き、取り残された午時葵の花を、撫でる様に手折った。
「また明日会おう」
FIN.