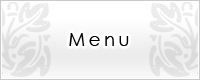19:嫉妬
刀と斧の刃先がギチギチと火花を散らし軋む。
不意に斧を持つ手を引くと、支えを失なったサルトビがよろける。
それを見とめてその細い脇腹に回し蹴りを入れると手応えがない。
バランスを崩しながらも私の動きを予見し、逆方向に跳んでいたのだ。
「腕を上げたな」
素直に関心し褒めると、サルトビはケ、と短く吐き捨て地面に手を付いた反動を利用し飛び掛かってくる。
アデュー達と合流して4日目、再戦しないかと持ちかけたのは私だった。
来たる邪竜族との戦いに備え、私達リュー使いは早急に腕を上げる必要があった。
精霊石を手に入れることもそうだが、クラスチェンジしたリューを使いこなすには乗り手の力が足りない。
それぞれが時間を見つけてはお互いに試合をして、強くなる為に苦心していた。
その為か、私の申し出は快諾された。
戦闘のスイッチが入ったサルトビの眼に、あの男の姿が浮かび上がってくるのを感じ、私は秘かに怖気をふるう。
叫びながら刀を振りかぶるサルトビをかわし斧の柄でその背中を突く。
「くっ…!」
堪らず倒れたサルトビだったがすぐに体を返し再び向かってこようとする。
「はい、お仕舞」
その鼻先に斧を突き付け、わざとらしく微笑んでやると、彼は悔しそうに唸った。
殺意が消え、負けず嫌いの少年の顔へと変わる。
張りつめた緊張の糸が切れ溜息を吐いたのは、勝った私の方なのだから笑ってしまう。
相変わらず、凄惨な戦い方をする。
憎しみを原動力に筋肉を動かし、重ねてきた修羅場に依って修練された武器捌き。
何度倒れても傷付いても、喉元に噛みつくように向かってくる。
自分の命を削る様な戦い方だ。
鍛錬の為、生活の為、そして国や主君を守る為に戦う私達武闘家とは違う。
――サルトビは、ガルデンに故郷を焼かれたのだ。
何も知らない私に、イズミがこっそりと教えてくれた。
そう聞いて私の頭に最初に浮かんだのは、負けた、という言葉だった。
武闘家としてサルトビの戦う理由の強さにではなく、サルトビの戦意を独占しているガルデンに、だ。
余りにも不謹慎で醜い感情に、自分でも驚いた。
同時に、私がサルトビに抱いている想いにも気付かされ、落胆もした。
私が惹かれた彼の強さは、最初から私に向けられることのないものだった。
サルトビにとって私はガルデンへの踏み台にしか過ぎず、私は彼と戦ってもいなかったのだ。
立ち上がって服についた土を払う彼は、私のそんな想い等知るよしもない。
私の方を見もしないその様子に、醜い嫉妬心が頭をもたげる。
「せっかく勝ったんだから、言うことを一つ聞いてもらおうかな」
「ああ?」
困らせたくなってそう言うと、サルトビは嫌そうに私の顔を見てくれた。
それだけで半ば満足してにっこり笑うと、一応の勝者の笑顔にあがらえないものを感じたのか、彼は腕を組んで顔を背けた。
「まあ、飯当番くらいなら代わってやってもいいけどよ」
「もっと簡単なことだよ」
あっさりと了承されたことに拍子抜けする。
だが、すぐに彼が「敗北」の重さを知っているからだと気が付き、じくりと胸が痛む。
もしかしたらこんな他愛もない遊びすら、彼の無意識化ではあの男に敗北した後に待つ仕打ちの予行練習なのかもしれない。
考え過ぎかとも思うが、そうなら私も仮初めの勝者として腹を括らなければならない。
「眼を瞑って」
「なんでだよ」
「いいから」
不服そうにしながらも、素直に目を閉じてじっとする、その少年らしい素直さに笑いそうになる。
吹き出すのを堪えながら近付いて、初めてまじまじとサルトビの顔を観察してみる。
奥二重であることも、睫毛が濃い茶色をしていることも、今初めて気が付いた。
手を伸ばしそっと頬に触れる。
ぴくんと頬の筋肉が小さく跳ねたが、慌てて「言うこと」を遂行するためにきつく目を閉じなおした。
今度こそ私は耐え切れず笑ってしまう。
「…さっさと済ませろよ」
笑われたことがプライドに触ったのか、目元をやや赤くして彼は文句を言う。
「ああ。分かったよ。すまないね」
もう片方の手も添えて、彼の顔を包む。
何をされるのか見当も付かず、サルトビの瞼が不安げに一度だけ痙攣した。
この薄い瞼の下の力ある眼に射抜かれたら、何も言えなくなる。
その狡さを見られないように眼を閉じさせた、私は本当に臆病者だ。
「君は、退くべきところをわきまえて利口に戦える筈なのに、時々そうではなくなるな」
「…」
サルトビは黙った。
自分でも解っているのだ。
あの男と対峙すると普段の冷静さを失ってしまう。
「復讐を遂げた後はどうするつもりだ」
「…そんなの、考えてねぇよ」
「もう少し、自分を…」
「心配しなくても、奴を殺すまでは死なねぇよ」
では、奴を殺した後は?
私の台詞を遮った彼の声の頑なさに、その一言が言えず、今度は私が黙った。
本当に、あの男を殺すヴィジョンは君の中にあるのか。
君はまだ15歳で、復讐を遂げた後にも人生は続いているはずなのに、そのヴィジョンが君から見えない。
あの男を殺して、その為に自分も死ぬ覚悟等、しないでくれ。
それではまるで心中ではないか。
「…もういいだろ」
沈黙に耐えかねてサルトビが開放を促し、私ははっと我に返る。
「すまないね、あと少し」
もう言えることも無いのに反射的にそう答えてしまい、それを聞いたサルトビがマスクの下で唇を不満げに固く結んだのが分かった。
だが明確な形までは見て取れない。
両の手で頬を包んでいるのに、布に阻まれ肌に触れることも出来ない。
私はサルトビの唇の形も、髪の色も、刻まれた傷の数も深さも知る術を持たない。
唯一露わになっている眼は、私を通り越してあの男を見る。
私は君から何も奪えず、それどころかまともに触れることすら叶わない。
だから、これ位は許して欲しい。
「ばっ…、馬っ鹿野郎!なにしやがんだ!」
私の悪ふざけに、サルトビは眼を見開いて跳ねるように退く。
予想通りの反応に、私は私は声を上げて笑ってしまった。
「マスクをしているんだからいいじゃないか。これ位はキスのうちに入らないよ」
「ったりめーだ!馬鹿!」
私の唇が触れたマスクの口元を、サルトビはしつこいほどに擦る。
目元を赤くして怒る少年に、笑いが止めらない。
何度でも立ち向かってくる、その執念が恐ろしかった。
初めて向けられる憎しみの籠った眼に臆した。
だが今は、その眼が私に向けられていないことが虚しく、君を失うことだけが怖い。
醜い感情は巧く、狡く隠してみせるから、束の間君の傍に居させて欲しい。
君を守る為に戦わせて欲しい。
しつこいほどに、君の良さを教えてあげよう。
君がその哀しい夢を叶える瞬間、死ぬのが惜しいと思えるように。
FIN.